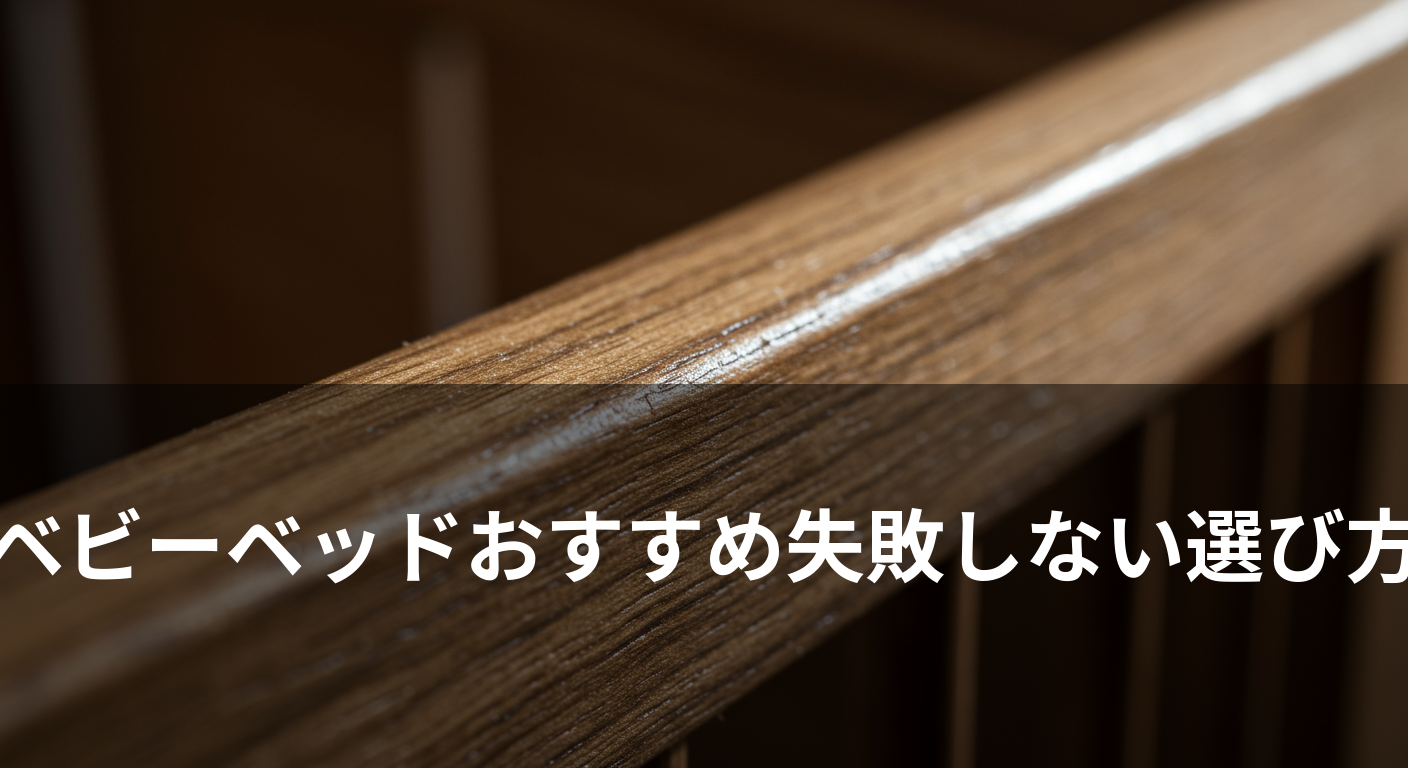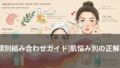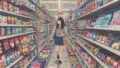出産を控えたあなたへ。
初めてのベビーベッド選びは、赤ちゃんの安全とママ・パパの育児負担を軽減するための大切なステップです。
たくさんある商品の中から、あなたのご家庭にぴったりの一台を見つけるために、この記事では失敗しないベビーベッド選びの重要なポイントと、様々なタイプの特徴を詳しくご紹介します。

あなたに最適なベビーベッドが見つかります
特に、安全性、設置場所とサイズ、使いやすさを決める高さという3つの具体的なポイントと、標準・ミニ・添い寝・多機能タイプそれぞれの特徴を知れば、迷わず最適なベビーベッドを選べます。
また、いつからいつまで使うか、レンタルか購入かといった疑問にもお答えします。
- ベビーベッドの必要性と安全を守る役割
- 失敗しない選び方:安全性、サイズ、高さ、機能、素材、価格
- 標準、ミニ、添い寝、多機能タイプ別の特徴と選び方
- いつからいつまで使うか、レンタル・購入、他の寝具との比較、片付け方
ベビーベッドが必要な理由と大切な役割
ベビーベッドが必要な最も重要な理由は、赤ちゃんの安全を守るためです。
ベビーベッドは、赤ちゃんの安全確保の役割、ママやパパの負担を軽減する役割、衛生的な睡眠環境を保つ役割、安心して過ごせる空間を作る役割、そして新生児期からすぐに利用できる点など、大切な役割を担っています。
これらの役割について詳しく見ていきましょう。
安全性確保の役割
ベビーベッドの最も大切な役割は、赤ちゃんの安全を確保することです。
大人のベッドや布団で添い寝をすると、赤ちゃんが柔らかい寝具に顔が埋もれて呼吸がしにくくなったり、寝返りした大人の体に押しつぶされてしまったりする危険性があります。
ベビーベッドは、赤ちゃん専用の安全なスペースを区切ることで、このような窒息のリスクを防ぎます。
柵があることで、赤ちゃんがベッドから誤って落ちてしまう転落事故も防止できます。
上にお子さんがいるご家庭やペットがいるご家庭では、ベビーベッドが赤ちゃんを不慮の接触から守る役割も果たします。
日本国内で販売されているベビーベッドの多くは、製品安全協会が定めた安全基準であるPSCマークが付与されています。
このマークは、製品の強度や柵の間隔(赤ちゃんの頭が挟まらないように例えば約8.5cm以下など)、耐久性といった項目について国の安全基準を満たしていることを示しています。
PSCマークが付いている製品を選ぶことは、赤ちゃんの安全を守る上で重要です。

赤ちゃんを予期せぬ事故から守る安全な場所になります
ベビーベッドは、赤ちゃんが安全に眠り、過ごせる環境を整えるために役立ちます。
ママやパパの負担を軽減
ベビーベッドは、ママやパパの育児の負担を軽減する役割も果たします。
特に、床から約60cm〜70cm程度の高さに赤ちゃんを寝かせられるハイタイプのベビーベッドは、かがむ回数が大幅に減ります。
オムツ替えや着替えといった作業を立ったまま行えるため、産後の体に大きな負担をかけがちな腰痛のリスクを軽減できます。
夜間の授乳が必要な際も、ハイタイプや大人のベッドの横に寄せられる添い寝タイプのベビーベッドなら、赤ちゃんの抱き上げや寝かせつけが楽な姿勢で行えます。
体勢を変える回数が減るため、夜間のお世話が少し楽に感じられます。

ママやパパの体をいたわる育児をサポートします
育児の負担が軽くなることで、ママやパパは赤ちゃんとの時間をより穏やかに楽しめます。
衛生的な睡眠環境
ベビーベッドは、赤ちゃんに衛生的な睡眠環境を提供する役割も担います。
床に近い空気中には、ハウスダストやホコリ、ダニなどが比較的多く存在しています。
ベビーベッドを使用すると、床から離れた位置に赤ちゃんを寝かせられるため、これらのアレルゲンから赤ちゃんを守る効果が期待できます。
また、多くのベビーベッドには床板の下にスペースがあり、ここにオムツ1パックや肌着数枚、おしりふきといった赤ちゃんのお世話グッズをまとめて収納できます。
これにより、部屋全体を整理整頓しやすくなり、結果として清潔な状態を保ちやすくなります。

赤ちゃんの周りの空気環境を清潔に保ちます
清潔な睡眠環境は、まだ体の機能が未発達な赤ちゃんの健康維持に役立ちます。
安心して過ごせる空間
ベビーベッドは、赤ちゃんに安全な居場所を提供することで、ママやパパが安心して過ごせる空間を作ります。
赤ちゃんがベビーベッドで安全に寝ている間は、ママがキッチンで簡単な軽食を用意したり、パパが仕事のメールをチェックしたりと、短時間であれば家事や別の作業に取り組むことができます。
常に赤ちゃんを抱っこしている必要がない時間があることで、ママやパパの心に少しゆとりが生まれます。
上のお子さんがいるご家庭では、ベビーベッド越しに赤ちゃんと触れ合う機会を設けることで、安全な形でコミュニケーションを促せます。

ママやパパの心にゆとりが生まれます
ベビーベッドがあることで、ご家族みんながより安心した気持ちで過ごせます。
新生児期からの利用
ベビーベッドは、一般的に新生児期からすぐに使用を開始できます。
「ベビーベッド いつからいつまで使うか」という疑問を抱えている方もいるかもしれません。
生まれたばかりの新生児期(生後0日から28日)から、つかまり立ちができるようになる生後8ヶ月頃まで、または赤ちゃんの体重が10kg程度になるまで使用するのが一般的な目安です。
ただし、使用期間は製品によって異なる場合があるため、事前に確認することが大切です。
つかまり立ちができるようになったら、安全のためベッドの床板を最も低い位置に設定し直す必要があります。
ベビーベッドが必要か、必要ないかという考え方がありますが、これはご家庭の環境や育児方針によって異なります。
例えば、実家への里帰り期間の約2週間だけ使用したい場合など、短期間の利用であれば購入ではなくレンタルを選ぶのも有効な選択肢の一つです。
| 使用期間の目安 |
|---|
| 新生児期から |
| つかまり立ちができる生後8ヶ月頃まで |
| 体重10kg程度まで |

赤ちゃんの成長に合わせて利用期間を考えましょう
いつからいつまで使うかをイメージすることで、購入かレンタルか、どのようなタイプのベビーベッドを選ぶかのヒントが見つかります。
ベビーベッドを選ぶ際の失敗しないチェックポイント
ベビーベッド選びで最も重要なのは、あなたの家庭環境やライフスタイルに合った一台を選ぶことです。
赤ちゃんの安全を守り、日々の育児を快適にするために、安全性、設置場所、使い勝手の3つを特に意識する必要があります。
この記事では、ベビーベッドを選ぶ際にチェックすべき以下のポイントを詳しく解説します。
設置場所と必要なサイズ、使いやすさを決める高さ、収納力や移動のしやすさ、素材と価格の比較、そして安全基準(PSCマーク)の確認についてご紹介します。
設置場所と必要なサイズ
ベビーベッドを設置する場所のサイズを事前に測ることは、失敗しない選び方の第一歩です。
特に都市部のマンションなど、居住スペースが限られているご家庭では、ベッドのサイズが部屋の広さや生活動線に大きく影響します。
日本で一般的なベビーベッドには、主に標準サイズ(内寸120cm×70cm)とミニサイズ(内寸90cm×60cm)があります。
ミニサイズは、標準サイズより縦横が30cmずつ小さいため、約0.3平米分のスペースを節約できます。
コンパクトなため、リビングの一角や夫婦の寝室など、設置したい場所に十分な広さがあるか、事前にメジャーを使って正確に測ることが重要です。
設置予定場所の壁から壁までの距離、窓やドア、既存の家具との位置関係を考慮して、最適なサイズを選びましょう。
- ベビーベッドの主なサイズ
- 標準サイズ: 内寸 120cm × 70cm (設置スペースにゆとりがある場合)
- ミニサイズ: 内寸 90cm × 60cm (コンパクトな住宅環境や一部屋を広く使いたい場合)

ベビーベッドの設置場所を決めたら、内寸だけでなく外寸も確認し、周囲の家具とのバランスを考えて選びましょう。
部屋の広さや形状、将来的な模様替えの可能性なども考慮に入れて、標準サイズかミニサイズか、あなたの家庭に最適なサイズのベビーベッドを選んでください。
使いやすさを決める高さ
ベビーベッドの床板の高さは、毎日の赤ちゃんとのお世話のしやすさに直接関わる重要なポイントです。
あなたが立った状態でお世話をすることが多いか、それとも床に座って過ごすことが多いかによって、選ぶべき高さが変わります。
一般的に、床板が高い位置にあるハイタイプのベビーベッドは、おむつ交換や着替えなどで赤ちゃんを頻繁に抱き上げる際に、腰を深くかがめる必要がなく、体の負担を軽減できます。
また、床からのホコリやハウスダストが届きにくい高さにあるため、衛生的な環境を保ちやすいでしょう。
一方、床板が低い位置にあるロータイプや、大人のベッドの高さに合わせられる添い寝タイプは、あなたが床に座って過ごす時間が長かったり、夜間にすぐそばで赤ちゃんのお世話をしたい場合に便利です。
製品によっては、赤ちゃんの成長に合わせて床板の高さを数段階に調整できる機能が付いています。
床のホコリから遠ざけられる | 立って家事や作業をすることが多い
赤ちゃんを抱き上げる機会が多い |
大人のベッドに高さを合わせやすい | 床に座って過ごすことが多い
寝室で大人のベッドに並べて添い寝したい |
| タイプ | 主なメリット | 適した利用シーン |
|---|---|---|
| ハイタイプ | 立ったままのお世話が楽、腰への負担が少ない | |
| ロータイプ | 床に座った状態でお世話がしやすい |

あなたの主な生活姿勢やお世話のスタイルに合わせて、最適な高さのベビーベッドを選びましょう。
特に床板の高さが調整できるタイプは、赤ちゃんの成長(首すわり前、つかまり立ち期など)に合わせて最適な高さに変えられるため、長い期間快適に使用できます。
収納力や移動のしやすさ
日々の育児に必要なものが多く、部屋が cluttered になりがちな中で、ベビーベッドの収納力や移動のしやすさは、使い勝手を大きく左右する機能です。
ベッド下に収納スペースがあるタイプは、おむつやおしり拭き、ベビーケア用品、タオルケットなど、よく使う育児グッズをまとめて保管できます。
オープン棚になっているものや、埃が入らないように引き出しタイプになっているものなど種類があります。
これにより、お世話の際に必要なものがすぐに手に届く場所にあり、効率よく育児を進めることができます。
また、部屋の中でベビーベッドを移動させたい場合には、スムーズに動かせるキャスターが付いているか確認が必要です。
キャスターには、移動しない時に固定できるロック機能が付いているものを選ぶと安全です。
里帰りや引っ越し、使わなくなった時にコンパクトに収納したい場合は、簡単に折りたためる機能が付いていると便利です。
立てて収納できるタイプや、専用の収納袋が付いているものもあります。
- 収納スペース: ベッド下におむつやケア用品をまとめて置ける(引き出しタイプ、オープンタイプなど)
- キャスター: 部屋間の移動や掃除の際に便利(ロック機能付きが安全)
- 折りたたみ機能: 使わない時の収納や持ち運びがしやすい(立てて収納可能、コンパクトに折りたためるなど)

あなたの部屋の広さや、どのようにベビーベッドを使用したいかに合わせて、必要な機能を検討しましょう。
収納スペースの容量や、キャスターのスムーズさ、折りたたみやすさなど、具体的な使い勝手をイメージしながら、あなたの生活に合った機能を持つベビーベッドを選びましょう。
素材と価格の比較
ベビーベッドの素材は、製品の耐久性やお手入れのしやすさ、部屋の雰囲気などに関わり、価格も素材やブランドによって大きく異なります。
一般的なベビーベッドの素材には、主に木製、プラスチック製、金属製があります。
木製のベビーベッドは、天然木の温かみがあり、落ち着いた雰囲気を醸し出します。
耐久性も高く、経年変化も楽しめます。
プラスチック製や金属製のベビーベッドは、比較的軽量で、フレームなどを水拭きできるためお手入れがしやすい製品が多い傾向があります。
また、組み立てや解体が比較的容易なものもあります。
価格帯は製品によって幅広く、シンプルな機能のものなら数千円から、多機能でデザイン性の高いものになると10万円を超える製品もあります。
一般的に、木製は中間から高価な価格帯、プラスチック製や金属製は比較的安価なものから中間価格帯の製品が多く見られます。
| 素材 | 主な特徴 | 価格帯(一般的な傾向) | お手入れ |
|---|---|---|---|
| 木製 | 温かみがある、耐久性が高い | 中間~高価 | 乾拭き、必要に応じて専用クリーナー |
| プラスチック | 軽量、お手入れしやすい、カラーバリエーション豊富 | 安価~中間 | 水拭き可能 |
| 金属 | 軽量、お手入れしやすい、シンプルなデザイン | 安価~中間 | 水拭き可能、サビに注意が必要な場合も |

予算だけでなく、素材ごとの特徴やお手入れ方法を考慮して、あなたにとって最適なベビーベッドを選びましょう。
ベビーベッド本体の価格だけでなく、一緒に購入するベビー布団やマットレス、シーツなどの寝具も含めた全体の費用を考慮して、予算計画を立てることが大切です。
安全基準(PSCマーク)の確認
ベビーベッドは、赤ちゃんが安全に過ごすための場所であるため、何よりも安全性が保証されている製品を選ぶことが最も重要です。
日本国内で販売されるベビーベッドには、国の定めた安全基準を満たしていることを示すPSCマークが付いているか必ず確認してください。
PSCマークは、製品安全協会が定める厳しい安全基準(SG基準)に適合した製品に付与されるマークで、ベビーベッドの安全基準は、柵の高さ、すき間の広さ、製品の強度、塗料の安全性など、様々な項目について定められています。
このマークが付いている製品は、第三者機関によって検査され、安全性が確認されています。
PSCマークは、ベビーベッド本体のシールやタグ、製品のパッケージ、取扱説明書などに表示されています。
- PSCマークは日本の製品安全基準に適合している証明
- PSCマーク付き製品は第三者機関による安全検査をクリアしている
- PSCマークの確認は、本体のシール、パッケージ、取扱説明書で行う

大切な赤ちゃんを事故から守るためにも、PSCマーク付きのベビーベッドを選ぶことは非常に重要です。
PSCマークの有無は、安全なベビーベッドを見分けるための最も重要な基準の一つです。
デザインや価格に惹かれて選ぶ場合でも、必ずPSCマークが付いていることを確認し、赤ちゃんの安全を第一に考えたベビーベッドを選びましょう。
あなたの生活に寄り添うベビーベッドタイプ別の特徴
あなたのご家庭にぴったりのベビーベッドを選ぶ上で、それぞれのタイプ別の特徴を知ることは大切です。
ここでは、標準サイズベビーベッド、ミニサイズベビーベッド、添い寝ベッドタイプ、多機能・折りたたみタイプ、そしてレンタルという選択肢についてご紹介します。
それぞれの特徴を理解し、あなたの生活に合ったタイプを見つけましょう。
標準サイズベビーベッド
標準サイズベビーベッドの内寸は120×70cmです。
このサイズは、多くのベビー布団セットがぴったり収まるサイズです。
赤ちゃんが寝返りを打ったり、つかまり立ちをするようになっても、比較的広々とした空間で過ごせます。
一般的に約2歳頃まで、または体重13kg程度まで使用できる商品が多く販売されています。
- 広々使えるサイズ感で、赤ちゃんの成長に合わせて長く使用できる
- 市場に出回っている種類が多く、デザインや機能の選択肢が豊富
- 市販されている様々なベビー寝具(布団、マット、シーツ)を合わせやすい

部屋のスペースに余裕があり、ベビーベッドを長期間利用したい場合に適しています
標準サイズは、赤ちゃんが活発に動くようになっても十分なスペースを確保できるため、安心感があります。
ミニサイズベビーベッド
ミニサイズベビーベッドの内寸は90×60cmです。
標準サイズよりも3割ほど小さく設計されています。
コンパクトさが最大の利点で、リビングや寝室などのスペースが限られているご家庭に適しています。
また、キャスター付きの商品が多く、部屋間の移動が簡単に行える点も便利です。
使用期間は、赤ちゃんがつかまり立ちを始める生後8ヶ月頃まで、または体重8kg程度までの商品が多い傾向があります。
| 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 内寸90×60cm | 省スペースで設置場所を選ばない、圧迫感がない | 標準サイズより使用できる期間が短い傾向がある |
| コンパクトな設計 | 部屋の模様替えや掃除の際に移動が楽、収納しやすい | 赤ちゃんが大きくなると手狭に感じる可能性がある |
| 短期間・一時利用向き | 里帰りなど、一時的な設置場所に適している | 専用サイズの寝具が必要になる場合が多い |

コンパクトさを重視するご家庭や、一時的にベビーベッドを使いたい場合にぴったりなサイズです
ミニサイズでも、SGマークなどの安全基準を満たした商品を選べば、標準サイズと同様に安全に使用できます。
添い寝ベッドタイプ
添い寝ベッドタイプは、大人用のベッドに並べて設置できるベビーベッドです。
大人のベッドのマットレスの高さに合わせて、ベビーベッドの床板の高さを調整できる商品が多く販売されています。
多くの商品で床板の高さを最低10cmから最高65cm程度まで、5cm刻みや無段階で調整できます。
ベビーベッドの側面の柵を開放して大人用ベッドに固定することで、夜間の授乳やおむつ替えがスムーズに行えます。
赤ちゃんの様子をすぐに確認できる安心感もあります。
- 大人用ベッドの高さに合わせられ、夜間のお世話が非常にしやすい
- 赤ちゃんを近くに感じながら安心して眠れる
- ベビーベッドの柵を開放した状態でも、大人用ベッドにしっかり固定できる機能がある
- 単独のベビーベッドとしても使用できる商品が多い

赤ちゃんと常に寄り添っていたい、夜間のお世話の負担を減らしたいというママやパパに選ばれています
大人のベッドとの間に隙間ができないように、付属の固定ベルトなどで確実に固定することが重要です。
多機能・折りたたみタイプ
多機能タイプには、様々な便利な機能が搭載されています。
例として、赤ちゃんの成長に合わせて床板の高さを数段階(3段階から5段階程度)調整できる機能があります。
これにより、首すわり前の低い位置、つかまり立ちする頃の高い位置など、状況に合わせて使い分けられます。
また、ベッド下の収納スペース付きの商品なら、おむつ約1パック分や着替え、お世話グッズをまとめて置くことができます。
さらに、キャスター付きなら部屋間の移動が簡単です。
一方、折りたたみタイプは、工具を使わずに数ステップで簡単に折りたためる商品があり、折りたたみ時の厚さが約20cm程度になり、クローゼットやベッド下にコンパクトに収納可能です。
| 機能 | 具体的な内容とベネフィット |
|---|---|
| 高さ調整機能 | 床板の高さを段階的に変更可能。お世話のしやすさや安全対策(つかまり立ち後)につながる |
| 収納スペース | ベッド下に広々としたスペース。おむつや小物をまとめて収納でき、スペースを有効活用できる |
| キャスター付き | 軽い力で部屋間の移動が可能。昼間はリビング、夜は寝室など、赤ちゃんの居場所を移動できる |
| 折りたたみ機能 | 使わない時にコンパクトに収納できる。保管場所に困らず、引っ越しや帰省時にも便利 |

赤ちゃんの成長や生活スタイルに合わせて、必要な機能を選びたい場合に適しています
これらの機能は、日々の育児の負担を軽減し、より快適にベビーベッドを使用するために役立ちます。
レンタルという選択肢
ベビーベッドの一般的な使用期間は、赤ちゃんがつかまり立ちを始める生後8ヶ月頃までです。
このように使用期間が比較的短いことから、購入するだけでなくレンタルサービスを利用するという選択肢も多くの方が選んでいます。
レンタルであれば、必要な期間だけベビーベッドを手元に置けます。
例えば、里帰り出産で実家で短期間だけ使用したい場合や、お試しでミニサイズを使ってみたい場合などに便利です。
レンタル会社によって期間設定は異なり、最短1週間から数ヶ月単位でレンタル可能です。
- 必要な期間(例えば1ヶ月や3ヶ月)だけベビーベッドを利用できる
- 購入するよりも初期費用や総費用を抑えられる場合がある
- 使わなくなったベビーベッドの処分方法を考える必要がない
- 人気のタイプ(ミニサイズやハイタイプなど)や商品を試せる機会になる

使用期間が限定されている場合や、購入前に実際に使ってみたい場合に有効な方法です
多くのレンタルサービスでは、ベビーベッドはしっかりとクリーニングされ、安全性が確認された状態で届けられます。
また、往復送料がレンタル料金に含まれているサービスもあります。
利用者の声で選ぶ人気のベビーベッドランキング
ベビーベッド選びで最も参考になるのは、実際に使った人の声です。
赤ちゃんの安全を守り、ママやパパの負担を軽くするためのベビーベッドは、たくさんの種類が販売されています。
ここでは、特に人気のあるベビーベッドの中から、利用者のリアルな感想や評価をご紹介します。
具体的な商品名とその特徴を比較しながら、あなたにとって最適な一台を見つける参考にしてください。
| 商品名 | タイプ | サイズ(内寸) | 重量 | 対象月齢 | 床板高さ調整 | 収納スペース | 特徴 | 価格帯(目安) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アップリカ ココネルエアープラス AB | 折りたたみ | 90×60cm | 9.5kg | 新生児〜24ヶ月 | 2段階 | 〇 | コンパクト収納、持ち運び | 3万円台後半 |
| カトージ ミニベッド 折りたたみ | ミニ・折りたたみ | 90×60cm | 11.1kg | 新生児〜24ヶ月 | 3段階 | — | シンプルな機能、手頃な価格 | 1万円台後半 |
| 大和屋 キホン ミニ | ミニ | 90×60cm | 11.5kg | 新生児〜24ヶ月 | 3段階 | — | 天然木、シンプルなデザイン | 2万円台前半 |
| ヤトミ ぐっすりベビーベッド | 標準 | 120×70cm | 12kg | 新生児〜24ヶ月 | 3段階 | 〇 | コストパフォーマンス | 1万円台前半 |
| キンタロー ミニベッド アンファン | ミニ | 90×60cm | 13.5kg | 新生児〜24ヶ月 | 3段階 | 〇 | 国産木材、安心の品質 | 2万円台後半 |
| 澤田木工所 ティアラ | 標準・ミニ | 120×70cm/90×60cm | 標準:約23kg ミニ:約17kg | 新生児〜24ヶ月 | 標準:4段階 ミニ:4段階 | 〇 | 国産ひのき材、高級感 | 標準:4万円台後半 ミニ:4万円台前半 |
※上記は代表的なモデルの一般的な情報です。
詳細な仕様や価格は各メーカーや販売店でご確認ください。
ご自身の重視するポイントに合わせて、それぞれの商品の詳細を見ていきましょう。
アップリカ ココネルエアープラス ABの人気の理由
多くの方に選ばれている人気の理由として特に重要なのは、アップリカ ココネルエアープラス ABならではの折りたたんでコンパクトになる使い勝手の良さと、赤ちゃんのための高い安全性です。
初めてベビーベッドを選ぶあなたにとって、多くの方が支持している製品は安心して検討できます。
アップリカ ココネルエアープラス ABは「対象月齢0ヶ月から24ヶ月」まで長く使え、「耐荷重10kg」まで対応しています。
また、「ミニサイズ」なので、都市部などの部屋が限られている環境でも約6畳程度のスペースにも無理なく設置が可能です。
- 工具不要で簡単に小さくたためる
- 専用バッグ付きで里帰りや旅行に持ち運びできる
- 通気性が高く、お手入れしやすいメッシュ素材の側板
- 床板下のスペースにおむつやお世話グッズを収納できる
- SG基準(製品安全協会基準)に適合している安全性

多くの人から支持される理由は、折りたたみ機能による使いやすさと安全性の高さにあります。
アップリカのココネルエアープラス ABが多くのママやパパに選ばれる最大の理由は、折りたたんでコンパクトになる使い勝手の良さにあります。
多くの利用者は、工具不要で簡単に小さくたためる点を挙げています。
例えば、実家に帰省する際に車に積んで持ち運んだり、使わない時期は部屋の隅やクローゼットに立てて保管したりできるため、場所を取らないと好評です。
ベッドを広げた状態でも、内寸90cm×60cmのミニサイズ設計なので、日本の一般的な住宅のリビングや寝室にも置きやすいと感じる方が多いです。
側面のメッシュ素材は通気性が高く、夏でも湿気がこもりにくく赤ちゃんが快適に過ごせます。
床板下には収納スペースも確保されており、おむつや肌着といったお世話グッズをまとめて置けます。
- 本体サイズ(開):幅1041mm × 奥行737mm × 高さ950mm
- 本体サイズ(閉):幅290mm × 奥行290mm × 高さ950mm
- 重量:16.0kg

限られたスペースを有効に使いたい方や、帰省などでベビーベッドを頻繁に持ち運びたいと考えている方に特に支持されています。
これらの特徴が、初めてベビーベッドを選ぶあなたにとって、安心して長く使える製品だと感じさせる人気の秘密です。
カトージ ミニベッド 折りたたみ のここが便利
カトージの「ミニベッド 折りたたみ」は、その名の通り「ミニサイズで場所を取らず、しかも折りたたみが可能」な点が大きなメリットです。
特に、都市部のマンションなど、赤ちゃんを迎えるスペースが限られているご家庭に選ばれています。
内寸90cm×60cmというコンパクトなサイズ感でありながら、ベッド下に収納スペースがあるモデルもあります。
また、多くのモデルにキャスターが付いているため、日中はリビングで、夜は寝室で赤ちゃんを寝かせたいといった場合でも、部屋間の移動がスムーズにできます。
さらに、床板の高さは3段階に調整できるものが多く、赤ちゃんの月齢に合わせてお世話がしやすい高さに設定できます。
- 省スペースで設置しやすいミニサイズ(内寸90cm×60cm)
- キャスター付きで部屋間の移動が楽である
- 床板の高さを3段階に調整できお世話がしやすい
- シンプル機能で価格もお手頃なモデルが多い

コンパクトさと移動のしやすさで、日々の育児がぐっと楽になります。
手狭な住宅環境にお住まいの方や、昼間と夜間でベッドの場所を変えたいという方にとって、非常に便利な機能が揃っています。
大和屋 キホン ミニを使ってみた感想
大和屋の「キホン ミニ」を利用した方々からは、「シンプルながら丈夫な作りで安心できる」「木の温もりが感じられるデザインが良い」といった感想がよく聞かれます。
天然木(パイン材)を使用しており、木目が美しく、どんなお部屋のインテリアにも馴染みやすいと好評です。
ベビーベッドとしての基本的な機能もしっかり備わっています。
床板は3段階に高さ調整できるため、赤ちゃんの成長に合わせて安全な高さを保てます。
例えば、新生児期はお世話のしやすい一番高い位置に、つかまり立ちを始めたら転落防止のために一番低い位置に変更するといった使い方ができます。
実際に使ってみると、「作りがしっかりしていて安定感がある」「赤ちゃんが中で手足をバタバタさせてもグラつかず安心」といった、安全面での安心感を評価する声も目立ちます。
- 天然木材(パイン材)を使用した温かみのあるデザイン
- シンプルでしっかりとした安定感のある構造
- 赤ちゃんの成長に合わせて床板高さが3段階調整可能
- 国内メーカー製で安心感がある

飾り気がないからこそ、木の良さが際立ち、長く使える魅力があります。
デザイン性はもちろん、赤ちゃんの安全をしっかり守る堅実な作りを重視したいという方におすすめです。
ヤトミ ぐっすりベビーベッドのコスパ評価
ヤトミの「ぐっすりベビーベッド」は、「価格が手頃なのに、ベビーベッドとして必要な機能と安全性を十分に備えている」と、コストパフォーマンスの高さで知られています。
出産準備にかかる費用は何かと大きくなるため、ベビーベッドは予算を抑えたいと考える方も多いでしょう。
この商品は、PSCマーク(日本のベビーベッドの安全基準)を取得しており、安心して使用できます。
内寸120cm×70cmの標準サイズと、90cm×60cmのミニサイズの両方があります。
床板下にはオープンタイプの収納棚があり、おむつやタオルなどをまとめて置けるので、散らかりがちなベビーグッズの整理に役立ちます。
特別な機能は少ないかもしれませんが、ベビーベッドとして求められる基本的な役割をしっかり果たしてくれる製品です。
- 販売価格が1万円台前半からと比較的手頃である
- PSCマーク付きで日本の安全基準を満たしている
- 標準サイズとミニサイズから選べる
- ベッド下収納が便利で実用的

必要な機能は抑えつつ、手頃な価格で手に入るのは大きなメリットです。
初めてのベビーベッドで、まずは基本的なものから試してみたい方や、できるだけ費用を抑えて準備したい方に適しています。
キンタロー ミニベッド アンファンと澤田木工所 ティアラを比較
キンタローの「ミニベッド アンファン」と、澤田木工所の「ティアラ(ミニ)」は、どちらも日本の木材を使用し、国内で製造されている安心感のあるミニベビーベッドです。
どちらを選ぶか迷った時に比較したいポイントを見てみましょう。
| 比較項目 | キンタロー ミニベッド アンファン | 澤田木工所 ティアラ (ミニ) |
|---|---|---|
| 主な素材 | 国産木材(パイン材など) | 国産ひのき材(無塗装) |
| 塗装 | エコウレタン塗装 | 無塗装 |
| 床板高さ調整 | 3段階 | 4段階 |
| 最大耐荷重 | 静止荷重約60kg(一例) | 静止荷重60kg(一例) |
| 特徴 | ネジ穴隠しシール付き、丸みのあるデザイン | ひのきの香りがリラックス効果、防カビ・抗菌効果 |
| 価格帯(目安) | 2万円台後半 | 4万円台前半 |

素材へのこだわりや、細部の仕様に違いがあります。
キンタローは、国産木材を使用しつつ、比較的リーズナブルな価格で購入できるバランスの良さが特徴です。
安全性に配慮したエコ塗装や、ネジ穴を隠すシールなど、細かい部分にも配慮が行き届いています。
一方、澤田木工所のティアラは、高級材である国産ひのきを無塗装で使用しており、ひのき本来の美しい木目や香りを楽しめます。
ひのきにはリラックス効果や防カビ・抗菌効果があると言われています。
また、床板の高さ調整が4段階と、より細かく設定できるのもメリットです。
天然素材や上質なものを長く使いたい方にはティアラ、国産材にこだわりつつ、コストパフォーマンスや使いやすさも重視したい方にはアンファンがおすすめです。
ベビーベッドの準備から使い始めるまで
ベビーベッドは、赤ちゃんが安全に眠るための大切なスペースです。
ここでは、ベビーベッドの準備から使い始めるまでの一連の流れについて解説します。
ベビーベッドはいつからいつまでベビーベッドを使うか、どんな必要なベビー寝具があるのか、レンタルか購入か迷ったらどちらが良いか、他の寝具との比較、そして不要になった時の片付け方など、具体的な疑問に答えます。
ベビーベッドを準備することは、新しい家族を迎えるための重要なステップの一つです。
正しい知識を持って準備を進めることで、赤ちゃんにとって安全で快適な環境を整えることができます。
いつからいつまでベビーベッドを使うか
ベビーベッドは、新生児期から使い始めるのが一般的です。
多くの赤ちゃんは、生まれてすぐからベビーベッドで過ごします。
いつまで使うかは、赤ちゃんの成長段階で判断します。
安全のために、赤ちゃんがつかまり立ちできるようになる生後8ヶ月頃から1歳半頃までを目安に使用する方が多くいます。
これは、赤ちゃんが自分でベッドの柵を乗り越えられるようになると、約1メートル近い高さから落下する危険があるためです。
ベビーベッドを使用する際は、商品の対象月齢や体重制限(多くの製品で10kgまたは13kg程度)を必ず確認してください。
これらの制限を超えての使用は危険を伴います。

赤ちゃんの安全を確保できる期間がベビーベッドの使用期間です
ベビーベッドの使用期間は、赤ちゃんの身体的な発達状況に合わせて柔軟に判断することが大切です。
必要なベビー寝具
ベビーベッド本体とは別に、赤ちゃんが安全で快適に眠るためのベビー寝具が必要です。
ベビーベッドで使用する主な寝具とその役割は以下の通りです。
| 寝具の種類 | 役割 |
|---|---|
| マットレス | 赤ちゃんの体を支え、骨格形成に配慮した適度な硬さが必要 |
| 敷き布団 | マットレスの上に敷くか、直接ベッドの床板に敷くことがあり、通気性が重要 |
| シーツ | 敷き布団やマットレスを汗や汚れから清潔に保ち、頻繁に交換するもの |
| 掛け布団 | 赤ちゃんの体温調節を助けるものだが、 SIDS予防のため軽いものが推奨される |
| 防水シーツ | おねしょなどで敷き布団やマットレスが汚れるのを防ぎ、洗濯可能なものが便利 |
新生児期は、SIDS(乳幼児突然死症候群)予防のため、うつぶせ寝を避け、顔の周りに物を置かないことが推奨されています。
柔らかすぎる枕や厚すぎる掛け布団の使用は避けてください。
赤ちゃんの月齢や季節、室温に合わせて適切なものを選びましょう。
例えば、夏場はガーゼケット1枚で十分な場合もあります。

赤ちゃんの安全と快適な睡眠環境のために適切な寝具を選びます
ベビーベッドと合わせて、これらの寝具を適切に揃えることで、赤ちゃんに安全で心地よい睡眠環境を提供できます。
レンタルか購入か迷ったら
ベビーベッドの準備にあたり、レンタルにするか購入するかで悩む方も多くいらっしゃいます。
どちらにもメリットとデメリットがあります。
レンタルと購入の比較
| 比較項目 | レンタル | 購入 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 月額数千円程度から利用でき、購入より安価に始められる | 安価なもので1万円台後半から、高価なものは10万円以上と価格帯が広い |
| 使用期間 | 短期間の利用、例えば数ヶ月の里帰り期間などに適している | 生後すぐから1年以上など、長期間利用する場合に費用対効果が高い |
| 手間のなさ | 不要になったら返却するだけで、処分や保管の手間がかからない | 使わなくなった後に、売却や処分、または保管する場所が必要となる |
| 種類の豊富さ | レンタル会社が提供する機種に限定され、最新モデルや特定のデザインは少ない | 実店舗やオンラインショップで多くの種類から自由に選択できる |
| 保管場所 | 必要ない | 次の子のために保管する場合や、すぐに手放さない場合は保管スペースが必要 |
| 清潔さ・状態 | 専門業者によるクリーニングが行われるが、使用感がある場合がある | 新品が手に入り、自分で清潔な状態を保てる |
数ヶ月程度の短期間だけ使いたい場合や、まず試しに使ってみたい場合はレンタルが便利です。
特にミニサイズや機能がシンプルなタイプはレンタルでも取り扱いが多いです。
一方で、数年以上使う予定がある場合や、きょうだいが産まれる可能性がある場合、デザインや機能にこだわりたい場合は購入が割安になることが多くあります。
ご家庭の状況、利用期間、そして不要になった後のことまで含めて検討してください。

利用期間や予算、不要になった後の手間を考慮して判断できます
レンタルと購入、どちらが良いかは、ご家族のライフスタイルや利用計画によって変わってきます。
それぞれの特徴を理解して、あなたに合う方法を選びましょう。
他の寝具との比較
ベビーベッド以外にも、赤ちゃんの寝具には選択肢があります。
他の寝具と比較することで、ベビーベッドを選ぶ理由やメリットがより分かりやすくなります。
ベビーベッドと他の主な寝具の比較
| 寝具の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ベビーベッド | 脚付きの囲い付きベッドで、床からの高さがある | 床のホコリや冷気から赤ちゃんを守り衛生的、ベッドからの落下を防ぐ囲いがあり安全、ハイタイプはお世話が楽 | ある程度の設置スペースが必要、他の寝具より価格が高めな傾向 |
| ベビー布団(床) | 赤ちゃん用の敷布団を直接フローリングや畳の上に敷く | ベッド本体が不要で省スペース、比較的安価に揃えられる | 床面のホコリやダニの影響を受けやすい、大人が踏んでしまうリスク、冬場は床からの冷気を感じやすい |
| 添い寝ベッド | 大人用ベッドに隣接して設置し、高さが調整できるベッド | 夜間の授乳やおむつ替えがしやすい、大人と同じ部屋で寝る安心感 | 大人用ベッドとの高さやフレーム形状の互換性を確認する必要がある |
| クーファン | 持ち手が付いた籠状の簡易ベッド | 赤ちゃんを寝かせたまま部屋間や外出先に移動できる、コンパクト | 使用できる期間が非常に短い(首がすわるまで等)、寝返りをするようになると安全性が低下する |
ベビーベッドは、床から数十センチ離れているため、舞い上がったホコリやハウスダストから赤ちゃんを守りやすく、衛生的な睡眠環境を提供できます。
また、ベッドの囲いがあることで、就寝中の大人が誤って赤ちゃんを圧迫してしまうリスクや、上のきょうだいやペットからの接触を防ぐことができます。
特にハイタイプのベビーベッドは、大人が立った姿勢でおむつ替えやお着替えをさせやすいため、産後のママの腰への負担を大きく軽減できます。
他の寝具も、例えば添い寝ベッドは夜間のお世話がしやすいなどそれぞれに利点があるため、ご家庭の環境、育児スタイル、生活スペースを考慮して選ぶことが大切です。

ご家庭の生活環境や育児方針に合う最適な寝具を見つけましょう
それぞれの寝具の特徴を理解し、メリット・デメリットを比較することで、あなたにとって本当に必要で使いやすいものを選ぶことができます。
不要になった時の片付け方
ベビーベッドを使わなくなったら、処分や活用方法を事前に考えておくとスムーズです。
いくつかの方法があります。
不要になったベビーベッドの主な片付け方
- 粗大ごみとして出す: 自治体によってルールが異なります。多くの場合、事前の予約が必要で、手数料がかかります。ベッドを分解する必要があるか、自宅前まで収集に来るか、指定場所まで運ぶ必要があるかなど、お住まいの自治体のウェブサイトや清掃事務所で確認が必要です。
- フリマアプリやオークションサイトで売る: まだ使用できる状態であれば、必要な人に譲ることができます。自分で商品の写真を撮影し、商品説明を記入、価格を設定し、購入者とのやり取り、梱包、発送手続きを行う手間がかかりますが、ある程度の収入が得られる可能性があります。
- リサイクルショップやベビー用品専門店に売る: 店舗に持ち込めば、その場で査定・買い取りしてもらえます。すぐに手放せるメリットがありますが、買い取り価格は安価な場合が多く、傷や汚れがひどい場合は買い取ってもらえないこともあります。事前に店舗に問い合わせるか、オンライン査定などを利用すると良いでしょう。
- 知人や親戚に譲る: 身近にこれから出産を迎える人や小さな子がいる人がいれば、直接譲ることができます。最も手軽な方法の一つですが、相手がベビーベッドを必要としているか、設置スペースがあるかなどを事前に確認が必要です。
- NPO法人や施設などに寄付する: 母子支援施設や児童養護施設、リサイクル活動を行っているNPO法人などでベビー用品を必要としている場合があります。事前に団体のウェブサイトを確認したり、問い合わせて受け入れ可能かを確認してから持ち込みや郵送の手配を行います。
どの方法を選ぶにしても、ベビーベッドを解体したり、きれいに掃除したり、付属品を揃えたりすることで、次の人に気持ちよく使ってもらえるように準備することが大切です。
破損している箇所がないか、安全に使用できる状態かも確認してください。

使わなくなった後のことも含めて計画を立てておくと慌てません
不要になったベビーベッドをどうするかは、その状態やあなたの希望によって最適な方法が異なります。
計画的に手放すことで、スムーズに片付けを進めることができます。
よくある質問(FAQ)
- Qベビーベッドは本当に必要ですか?いらない人もいますか?
- A
ベビーベッドは必須ではありませんが、赤ちゃんの安全確保、ママやパパの負担軽減、衛生的な睡眠環境の維持に役立ちます。
具体的には、大人の布団での窒息や転落を防ぎ、上の子やペットからの接触から赤ちゃんを守る役割があります。
ハイタイプを選べば、おむつ交換などでかがむ回数が減り、腰への負担を軽減できます。
また、床のホコリやダニから赤ちゃんを遠ざけられる衛生的なメリットもあります。
一方で、ご家族の添い寝を重視する場合や、部屋のスペースが限られている場合は、ベビー布団を敷いたり、添い寝用の簡易ベッドで対応したりする方もいらっしゃいます。
ご自身のライフスタイルやご家庭の環境に合わせて検討してください。
- Qベビーベッドはいつからいつまで使えますか?
- A
一般的に、ベビーベッドは生まれたばかりの新生児からすぐに使用を開始します。
いつまで使うかは、赤ちゃんの安全を最優先に考えることが大切です。
赤ちゃんがつかまり立ちできるようになる生後8ヶ月頃から1歳半頃までを目安に使用する方が多いです。
赤ちゃんが自分でベッドの柵を乗り越えられるようになると非常に危険ですので、そうなる前に使用を終了しましょう。
各製品に記載されている対象月齢や体重制限も確認しながら、赤ちゃんの成長段階に合わせて判断します。
- Q部屋が狭いのですが、コンパクトなベビーベッドはありますか?
- A
はい、部屋のスペースが限られているご家庭には、ミニサイズのベビーベッドがおすすめです。
一般的な標準サイズ(内寸120cm×70cm)よりコンパクトな内寸90cm×60cm程度のものが主流です。
これなら都市部のマンションなどの限られたスペースにも比較的置きやすく、部屋全体に圧迫感もありません。
キャスター付きを選べば、掃除や模様替え、昼間はリビング、夜は寝室といった部屋間の移動も便利に使えます。
ミニサイズのベビーベッドでも、安全基準を満たした商品が多く販売されています。
- Q購入ではなく、ベビーベッドをレンタルするメリットは何ですか?
- A
ベビーベッドをレンタルする主なメリットは、必要な期間だけ手軽に利用できることです。
例えば、里帰り出産で実家で短期間だけベビーベッドを使いたい場合や、ベビーベッドが必要か迷っていてまずお試しに使ってみたい場合に、購入するよりも費用を抑えられる可能性があります。
使い終わった後の解体や粗大ごみとしての処分方法を考える手間がない点もメリットです。
また、人気の高機能なモデルを購入前にお試しでレンタルすることもできます。
- Q大人用ベッドと添い寝できるタイプのベビーベッドはありますか?
- A
はい、大人用ベッドに隣接させて使える添い寝ベッドタイプがあります。
多くの添い寝タイプは、ベビーベッドの床板の高さを大人用ベッドのマットレスの高さに合わせて細かく調整できます。
ベビーベッドの側面を開けて大人用ベッドにしっかりと固定することで、夜間の授乳やおむつ替えの際、赤ちゃんをすぐに近くでお世話できます。
赤ちゃんを常にそばに感じられるため、ママやパパは安心して眠れます。
使用の際は、大人用ベッドとの間に赤ちゃんが落ちるような隙間ができないよう、付属の固定ベルトなどで確実に固定することが重要です。
- Q失敗しないためのベビーベッド選びで、特に重要なポイントは何ですか?
- A
失敗しないベビーベッド選びで最も重要なのは、赤ちゃんの安全性を確保することです。
日本の製品安全基準に適合したことを示すPSCマークが付いているか必ず確認しましょう。
次に、ご自宅の設置予定場所のスペースをメジャーで正確に測り、標準サイズかミニサイズかを決めます。
そして、日々のお世話が楽になる高さも重要です。
腰への負担を減らしたいなら立ったままお世話しやすいハイタイプ、床に座って過ごすことが多いならロータイプなど、お世話する方の身長や生活スタイルに合わせた高さがおすすめです。
ベッド下の収納スペースや移動に便利なキャスターなど、ご自身の生活であると便利な機能も検討材料になります。
まとめ
出産準備で大切なベビーベッド選びについて、失敗しないためのポイントやタイプ別の特徴をご紹介しました。
たくさんの商品の中から、あなたのご家庭にぴったりのベビーベッドを見つけるには、赤ちゃんの安全確保を第一に考えることが重要です。
特に、日本の安全基準であるPSCマークが付いているか確認することが最も重要です。
- 安全性を証明するPSCマークの確認
- 設置場所や用途で選ぶサイズ(標準・ミニ)と高さ
- 育児を楽にする収納・キャスター・折りたたみ機能
- 具体的な人気商品名とそれぞれの特徴
この記事で解説した失敗しない選び方や具体的な商品情報を参考に、ご家庭に最適なベビーベッドを見つけて、新しい家族を迎える準備を進めてください。
実際に商品を見て、ご自身に合ったものを選ぶことをおすすめします。