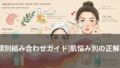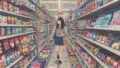赤ちゃんの歩き始めの時期は、いつから? 周りの子と比べて「うちの子はまだかな…」と心配になることもありますよね。
赤ちゃんの成長ペースには大きな個人差があることを知っておくことが大切です。
この記事では、赤ちゃんが一人で歩き始める一般的な時期の目安や、歩行に向けて見られるサイン、もしなかなか歩き始めなくても焦らなくて大丈夫な理由、そして親ができるサポート方法について、専門家の知見も踏まえながら解説します。

赤ちゃんの成長は一人ひとり違います、焦らず見守りましょう
この記事でわかること
- 赤ちゃんが歩き始める一般的な時期の目安
- 歩き始める前に見られるサイン
- もし歩き始めが遅くても大丈夫な場合と心配なサインの見極め方
- 赤ちゃんが安全に歩くためのサポート方法
| 見出し | 内容 |
|---|---|
| 歩き始めの時期は人それぞれということ | ・歩くまでに首すわりなど段階を踏む過程 ・一般的な目安は11ヶ月から1歳3ヶ月頃 ・気質や発達ペース、環境で個人差があること ・他の子と比べず焦らず見守る姿勢 |
| 赤ちゃんが歩き始める時期と見られるサイン | ・一人で歩くのは11ヶ月から1歳3ヶ月頃が多い ・手を使わず立つなど歩行準備のサインが見られる ・つかまり立ちや伝い歩きは重要な練習過程 ・全身でバランスをとる動きが増えること |
| もし赤ちゃんがなかなか歩き始めなくても | ・1歳過ぎて歩き始めなくても焦らない ・1歳半は健診の目安だが個人差は大きい ・他の発達が順調なら多くは心配不要 ・他の発達遅れなどが心配なサイン |
| 赤ちゃんの歩行をサポートする方法と心構え | ・家庭内の危険対策など安全な環境作り ・声かけや一緒に歩くなど意欲を育む働きかけ ・サイズや素材など適切な靴を選ぶポイント ・転んでも見守り個人差を受け止める心構え |
| 見出し | 内容 |
|---|---|
| 歩き始めの時期は人それぞれということ | ・歩けるようになるまで段階を踏む ・一般的な時期は11ヶ月〜1歳3ヶ月頃だが個人差がある ・気質や環境など多くの要因が影響 ・他の子と比べず、その子のペースを見守る大切さ |
| 赤ちゃんが歩き始める時期と見られるサイン | ・一人で数歩歩くのは11ヶ月〜1歳3ヶ月頃が多い目安 ・立ったまま座る、手を使わず立つなど準備のサインが見られる ・つかまり立ちや伝い歩きで体のバランスや足の動きを練習 ・様々な動きで全身のバランス感覚を養っている |
| もし赤ちゃんがなかなか歩き始めなくても | ・1歳を過ぎても焦る必要はなく珍しくない ・1歳半は健診で発達を確認する目安時期 ・慎重な性格やハイハイ十分など遅くても大丈夫な場合が多い ・他の発達の遅れなど心配なサインがあれば専門家へ相談 |
歩き始めの時期は人それぞれということ
お子さんが歩き始める時期は、一人ひとり違いがあるのが自然なことです。
赤ちゃんが一人で歩けるようになるまでには、体の機能やバランス感覚の発達が必要です。
この章では、歩行に至るまでの歩行までの発達は段階を踏むこと、一般的な月齢の目安、歩き始める時期に個人差がある理由、そして親御さんが意識したい他の子と比べすぎない大切さについて説明します。
周りの赤ちゃんと比べて「うちの子はまだかな」と心配になるかもしれません。
しかし、焦らず、お子さんのペースを見守り、寄り添うことが何より大切です。
歩行までの発達は段階を踏む
赤ちゃんが自分で立って歩けるようになるまでには、いくつかの発達の段階があります。
それぞれの段階で、体全体の筋肉を強くしたり、バランスを取る練習をしたりしています。
首がすわる、寝返りをする、お座りをする、ハイハイをする、つかまり立ちをする、伝い歩きをするなど、一つひとつの動きを通して、赤ちゃんは地面から離れて体を支えるための準備を進めます。
これらの積み重ねが、やがて自分で立って歩く力になるのです。
- 首すわり
- 寝返り
- お座り
- ハイハイ
- つかまり立ち
- 伝い歩き

発達には順番があります
赤ちゃんは自分で体をコントロールする方法を、こうした段階を追って少しずつ学んでいきます。
一般的な月齢の目安
多くの場合、赤ちゃんは生後11ヶ月から1歳3ヶ月頃に初めて一人で数歩歩くようになります。
これはあくまで一般的な平均的な目安です。
統計的にはこの時期に歩き始める赤ちゃんが多いという事実を示しています。
しかし、赤ちゃんの成長のペースは一人ひとり違います。
早い子では生後10ヶ月頃から、ゆっくりな子でも1歳半頃までに歩き始めることがよくあります。
- 一般的な開始時期: 生後11ヶ月頃
- 多くの子が歩く時期: 1歳から1歳3ヶ月頃
- 個人差がある終了時期: 1歳半頃

あくまで目安として考えましょう
この目安よりも遅いからといって、すぐに発達に問題があるわけではありません。
歩き始める時期に個人差がある理由
赤ちゃんが歩き始める時期に差が出るのには、いくつかの理由があります。
生まれ持った気質や体の発達のペースが関係します。
たとえば、活発で体を動かすのが好きな赤ちゃんは早くから動き回る傾向があります。
また、つかまり立ちや伝い歩きを始めるまでの期間や、ハイハイの期間が長いか短いかによっても、歩き始めのタイミングは変わります。
育つ環境、たとえば家の中の広さや、どれだけ自由に動き回れるスペースがあるか、親御さんがどのように関わるかなども影響します。
- 生まれつきの気質や性格
- 体の発達のペース
- ハイハイをする期間
- 自由に体を動かす機会の量

生まれ持った個性や環境が影響します
個人差は成長の証です。
さまざまな要因が組み合わさって、それぞれの赤ちゃんのペースが決まります。
他の子と比べすぎない大切さ
お子さんの成長を見ていると、どうしても周りの同じ月齢の子と比べてしまうことがあるかもしれません。
「あの子はもう歩いているのに」と感じて、不安になるのは自然なことです。
しかし、他の子と比べすぎる必要はありません。
比較しすぎることで、親御さんが必要以上に焦りを感じたり、それがお子さんにも伝わってしまったりする可能性があります。
何より、お子さん自身の持っている個性や、その子のペースで一生懸命頑張っている姿を見落としてしまうかもしれません。
- 親が焦りを感じる
- お子さんにプレッシャーを与える
- お子さんの個性を見落とす

お子さんのペースを見守ることに集中しましょう
一番大切なのは、今のお子さんがどのように成長しているか、その子自身の変化に目を向けることです。
温かい気持ちで見守ってあげてください。
赤ちゃんが歩き始める時期と見られるサイン
赤ちゃんの成長には個人差がありますが、多くの赤ちゃんが歩き始める前にはいくつかの具体的なサインが見られます。
これらのサインを知ることは、お子さんが歩き始める準備ができているかを知る上で大切な目安になります。
これらのサインは、赤ちゃんが一人で数歩歩くことが多い一般的な月齢、体が歩行に向けて準備をしている「歩行の準備ができているサイン」、つかまり立ちからステップアップする「つかまり立ちから伝い歩きへの変化」、そして全身を使ってバランス感覚を養う「体をバランス良く使う動きが増える」といった、様々な発達の段階を通して現れてきます。
これらのサインを見つけることで、今お子さんの体がどのような準備をしているのかを理解し、安心して成長を見守ることができるでしょう。
一人で数歩歩くことが多い月齢
赤ちゃんが「一人で数歩歩く」ようになる月齢は、一般的に生後11ヶ月から1歳3ヶ月頃です。
これはあくまで多くの赤ちゃんに見られる傾向であり、平均的な目安として知られています。
早い赤ちゃんでは10ヶ月頃から歩き始めることもありますし、ゆっくりな赤ちゃんでも1歳半頃までに歩き始めることがよくあります。
成長のペースはお子さん一人ひとり違うものです。

一般的な月齢を知ることで目安にはなりますね
一般的な月齢は一つの参考情報として捉え、大切なお子さんのペースを尊重してあげましょう。
歩行の準備ができているサイン
赤ちゃんが歩行に向けて体の準備を進めているときには、さまざまな「歩行の準備ができているサイン」が見られます。
たとえば、立った状態からお尻を上手について座れるようになったり、家具などにつかまらずに手だけでお座りから立ち上がろうとしたりするようになります。
また、高い高いをしても両足を突っ張って立とうとしたり、膝や肘を使った運動能力が高まることもサインです。
| サイン | 様子 |
|---|---|
| 立った状態からの着地 | お尻からスムーズに座れるようになる |
| 立ち上がりの動作 | 手を使わずにお座りから立とうとする |
| 高い高い時の足の動き | 両足を突っ張って立つようにする |
| 運動能力の発達 | 膝や肘を使った動きが活発になる |
| つたい歩きの安定 | より長い距離をスムーズに移動する |
| 何も持たずに立つ時間 | 数秒間バランスを保てるようになる |

これらのサインは歩くための土台作りが進んでいる証拠です
たくさんのサインは、お子さんが着実に歩くための体の使い方やバランス感覚を身につけている証拠です。
つかまり立ちから伝い歩きへの変化
赤ちゃんが一人で歩けるようになる前に、多くの赤ちゃんが経験するのが「つかまり立ち」と、そこから派生する「伝い歩き」です。
まず、家具や壁などに手をついて自分で立ち上がる「つかまり立ち」ができるようになります。
つかまり立ちで体の縦のバランス感覚を養った後、家具などに捕まりながら横に移動する「伝い歩き」を始めます。
この伝い歩きを通して、足を左右に動かすこと、バランスを崩したときに立て直すことなどを繰り返し練習しています。
この段階は、一人でバランスを取りながら前に進むための重要なステップとなります。

つかまり立ちや伝い歩きは歩くための練習です
つかまり立ちや伝い歩きでの経験が、一人で歩くための土台となります。
体をバランス良く使う動きが増える
赤ちゃんが歩くためには、単に足の力だけでなく、全身を使って「バランス良く体をコントロールする」能力が欠かせません。
たとえば、立った状態からお尻を上手について座る動作や、手を使わずにお座りから立ち上がる動作は、体の重心移動とバランスの取り方を練習しています。
また、おもちゃを取ろうと体をねじったり、少し不安定な場所でも姿勢を保とうとしたりする動きも、体の軸を感じてバランスを取る練習になっています。
このような多様な動きを通して、歩行に必要なバランス感覚を養っています。
| バランス練習になる動き | 様子 |
|---|---|
| 座る練習 | 立った状態からお尻で着地 |
| 立つ練習 | 手を使わずにお座りから立ち上がり |
| 体のねじり | おもちゃを取ろうと上半身を回す |
| 不安定な場所での調整 | 絨毯の上などで姿勢を保つ |
| 片足立ちの瞬間 | 体重移動をする際に瞬間的に片足に |

いろいろな動きがバランス感覚を育てています
日々の様々な体の動きが、歩行に必要なバランス能力を高めるトレーニングにつながっています。
もし赤ちゃんがなかなか歩き始めなくても
赤ちゃんがなかなか歩き始めないと、心配になる親御さんもいらっしゃいます。
でも、焦る必要はありません。
歩き始めの時期には大きな個人差があり、1歳半が一つの目安にはなりますが、それより遅い場合でも大丈夫なケースはたくさんあります。
この記事では、遅いように見えても大丈夫な場合や、心配なサインの見極め方、そして必要な場合に専門機関へ相談するタイミングについて詳しくお伝えします。
大切なのは、焦らず、お子さんのペースを見守りながら、必要に応じて適切な情報を得てサポートすることです。
1歳を過ぎた場合の考え方
赤ちゃんが一人で歩き始める時期は、一般的に生後11ヶ月から1歳3ヶ月頃と言われていますが、これはあくまで平均的な目安です。
1歳を過ぎてから歩き始めるお子さんもたくさんいらっしゃいます。
例えば、ハイハイや伝い歩きを十分に経験して、より体の基礎ができている場合などです。
他の発達(首すわり、お座り、ハイハイなど)が順調に進んでいるのであれば、1歳を過ぎてもすぐに心配する必要はありません。

1歳を過ぎても焦る必要はありません。
1歳を過ぎても歩き始めないことは珍しいことではありません。
大切なのは、その子の他の発達段階も見て、総合的に判断することです。
1歳半が一つの目安となる理由
1歳半という時期が目安とされるのは、主に乳幼児健診のスケジュールに関係しています。
多くの自治体で1歳半健診が行われ、この健診で運動発達(歩行を含む)、言葉の発達、社会性など、様々な項目が専門家によって確認されます。
この時期までに多くの発達マイルストーンが確認できるようになるため、1歳半が一般的なチェックポイントとして設けられています。
専門家がお子さんの発達状況を評価する上で、この時期が一つの節目となっているのです。

1歳半健診は発達の確認の場です。
1歳半は、専門家が発達を確認する上での一般的な目安ではありますが、すべての子がこの時期までに完璧に歩けているわけではありません。
目安として知りつつも、個別の状況を見守ることが大切です。
遅いように見えても大丈夫な場合
歩き始めるのが遅いからといって、必ずしも発達に問題があるわけではありません。
遅い理由には、お子さんの個性や気質(例えば慎重な性格)、あるいはハイハイをたくさん経験していることなどが挙げられます。
特に、ハイハイをしっかり行うことは、体のバランス感覚や筋力を養う上で非常に重要です。
ハイハイ期間が長かった子ほど、歩き始めてからの転倒が少ないという報告もあります。
また、安全に探索できる周りの環境が整っているかどうかも影響することがあります。
| 遅いように見えても大丈夫なケース | 具体的な状況 |
|---|---|
| 個性や気質 | 慎重な性格の子など |
| ハイハイを十分に経験している | バランス感覚や筋力が養われる |
| 探索できる安全な環境が整っている | 自由に動き回れている |

遅めのスタートでも、豊かな経験につながります。
歩き始めが遅いこと自体が問題なのではなく、その背景にある他の発達が順調であれば、多くの場合は心配いりません。
じっくりと体の準備をしている証拠とも言えます。
心配なサインの見極め
歩行以外の他の発達マイルストーン(首すわり、お座り、ハイハイなど)にも著しい遅れが見られる場合や、特定の動作に明らかな左右差がある場合、手足の動きが硬すぎる・柔らかすぎると感じる場合などは、注意が必要なサインかもしれません。
例えば、1歳を過ぎても首すわりやお座りが不安定だったり、両手足で同じ動きを繰り返すばかりで多様な動きが見られないなどです。
これらのサインは、専門家による評価が必要な場合があるため、見逃さないようにすることが大切です。
| 心配なサインと考えられる例 | 具体的な様子 |
|---|---|
| 他の発達マイルストーンに遅れ | 首すわり、お座り、ハイハイなどが目安時期を大幅に過ぎている |
| 体の特定の動きに左右差がある | 片方の手足ばかり使う、片側への傾きが強いなど |
| 手足の動きが硬すぎる、または極端に柔らかいと感じる | 関節の動きがスムーズでない、ぐにゃぐにゃしているなど |

心配なサインがある場合は専門家へ相談を。
これらのサインはあくまで一例であり、必ずしも問題を示すわけではありませんが、気になる場合は自己判断せず、専門家の意見を求めることが最も安心できる方法です。
専門機関へ相談するタイミング
もし心配なサインに当てはまる場合や、不安な気持ちが続く場合は、専門機関へ相談してみることをお勧めします。
1歳半健診で相談してみたり、日常的に通っているかかりつけの小児科医に何気なく聞いてみたりするのも良いタイミングです。
また、お住まいの自治体にある子育て支援センターや保健センターでは、専門の保健師などが相談に乗ってくれます。
特に、1歳半を過ぎても一人で歩き始めない場合は、相談してみましょう。
専門家は、発達状況を正確に評価し、具体的なアドバイスや必要に応じたサポートにつなげてくれます。
| 相談できる専門機関 | 相談内容や役割 |
|---|---|
| 市町村の乳幼児健診 | 定期的な発達チェックの機会 |
| かかりつけの小児科医 | 日常的な体調の相談、発達の懸念へのアドバイス |
| 保健センター/子育て支援センター | 保健師や専門家による育児や発達全般の相談支援 |
| 児童発達支援センターなど | より専門的な評価や療育が必要な場合の相談先 |

一人で抱え込まず、まずは気軽に相談してみましょう。
不安を感じた時は、抱え込まずに専門機関へ気軽に相談することが大切です。
専門家のアドバイスを聞くことで、安心して見守ることができるようになったり、必要なサポートを受けられたりします。
赤ちゃんの歩行をサポートする方法と心構え
赤ちゃんが安全に、そして楽しく歩き始めるためには、周囲のサポートとあたたかい見守りが重要です。
家庭での安全な環境づくりから、歩く意欲を育む働きかけ、適切な靴選び、そして転んだ時の見守り方まで、具体的な方法を知ることで、安心して成長を見守ることができます。
家庭での安全な環境づくり
赤ちゃんが自由に探索し、体を動かせる安全な環境を用意することは、歩行に必要な筋力やバランス感覚を養う基盤となります。
家庭内の安全を確認し、赤ちゃんが活動しやすい空間を作りましょう。
赤ちゃんが動き回るようになる前に、家の中の危険な場所や物を整理しておくことが大切です。
床に滑りやすい物がないか確認し、電気コードや家具の角など、赤ちゃんにとって危険になりうる箇所に安全対策を施します。
| 確認ポイント | 具体的な対策 |
|---|---|
| 床 | 滑りにくいラグを敷く、液体などをすぐに拭く |
| 家具の角 | コーナーガードを取り付ける |
| コンセント | コンセントカバーを取り付ける |
| 階段や段差 | ベビーゲートを設置する |
| 高い場所にある物 | 落下しやすい物を片付ける |
| 割れやすい物 | 赤ちゃんの届く範囲に置かない |
| 小さな部品や誤飲の危険がある物 | 赤ちゃんの届かない場所に保管する |

赤ちゃんが安心して動き回れる環境が、自立した歩行への第一歩につながります
安全な環境は、赤ちゃんが失敗を恐れずに挑戦できる気持ちを育みます。
歩く意欲を育む働きかけ
赤ちゃんが「歩きたい」という気持ちを持つように、保護者の方からのあたたかい働きかけが大きな力となります。
楽しんで体を動かす機会を増やす工夫をしてみましょう。
歩くことへの興味を引くために、赤ちゃんの手を持って数歩一緒に歩いてみる、「あっちに行ってみようか」と声かけながら好きな物がある場所へ誘導するなどの方法があります。
成功体験を褒めてあげることで、赤ちゃんは自信を持って次のステップへ進みます。
| 具体的な働きかけ | ポイント |
|---|---|
| 声かけと誘い | 「〇〇取りに行こうか」と楽しく話しかける |
| 手を引いて一緒に歩く | 赤ちゃんのペースに合わせて、無理強いしない |
| 好きな物で誘導 | 少し離れた場所におもちゃを置き、取りに行かせる |
| 成功したら褒める | 「できたね!」「すごい!」と笑顔で伝える |
| 動きやすい服装を選ぶ | 動きを妨げない、通気性の良い服を着せる |
| 十分な休息と栄養確保 | 体力が必要なので、生活リズムを整える |

遊びを通して体を動かす楽しさを知り、歩くことへの意欲が高まります
焦らず、赤ちゃんの「やりたい」気持ちを尊重しながら寄り添うことが大切です。
初めて靴を選ぶポイント
赤ちゃんが屋外で歩き始める頃になったら、足を守り、正しい歩行をサポートするファーストシューズを考えましょう。
適切な靴選びは、赤ちゃんの足の健やかな成長に影響します。
ファーストシューズを選ぶ際は、赤ちゃんの足のサイズにしっかり合わせることが最も重要です。
つま先に5mmから1cm程度のゆとりがあるか、足の甲がフィットしているかなどを確認します。
また、靴底が柔らかく、指の付け根あたりで自然に曲がるか、通気性が良いかどうかも選ぶ上での大切な基準です。
| 靴選びのポイント | チェック項目 |
|---|---|
| サイズ感 | 足長+0.5~1cmのつま先のゆとり、足囲が合っているか |
| 靴底(ソール) | 柔らかく、曲がりやすいか(指の付け根部分) |
| 素材と通気性 | 軽量で通気性の良い素材か |
| かかと部分のフィット感 | 硬さがあり、しっかり足を支えられるか |
| 履かせやすさ | 開きが大きく、着脱しやすいか(マジックテープなど) |
| 重さ | 赤ちゃんの負担にならない軽い靴か |

赤ちゃんの足の形や成長に合った靴を選ぶことが、歩行のサポートにつながります
お店で専門の方に見てもらうのも良い方法です。
ファーストシューズの役割と慣らし方
ファーストシューズは、単に足を保護するだけでなく、まだ未熟な赤ちゃんの足や足首を支え、正しい歩行を促す重要な役割があります。
地面からの刺激を和らげ、安定して歩く練習を助けてくれます。
初めて靴を履く赤ちゃんは、感触に慣れていないため嫌がることもあります。
最初は家の中で短時間だけ履かせて、靴を履くことに慣れさせましょう。
お散歩に行くときに履くなど、楽しい経験と結びつけると受け入れやすくなります。
| ファーストシューズの慣らし方 | 具体的なステップ |
|---|---|
| 室内で短時間から | 家の中で10分~20分程度履かせてみる |
| 少しずつ時間を延ばす | 慣れてきたら時間を長くしていく |
| 楽しい経験と結びつける | 靴を履いておもちゃで遊ぶ、外に出る前に履く |
| 毎日履かせる習慣にする | 生活の一部に取り入れる |
| 履かせたまま様子を見る | 赤ちゃんの様子を見て、嫌がらないか確認 |

靴は歩くための大切な道具であることを、赤ちゃんにゆっくり教えていきましょう
無理強いせず、赤ちゃんのペースに合わせて進めることが大切です。
転んでも見守る保護者の姿勢
赤ちゃんが歩き始めると、転ぶ回数が増えます。
転ぶことは失敗ではなく、体の使い方やバランスの取り方を学ぶための大切な過程です。
過度に心配せず、安全な場所であれば見守る姿勢を持ちましょう。
転んだときにすぐに駆け寄って抱き上げるのではなく、まずは赤ちゃんの様子を見守ります。
自分で起き上がろうとするのを待ち、できたときにはたくさん褒めてあげましょう。
大きな怪我につながらないよう、周囲の安全確保はしっかり行っておくことが前提です。
| 見守りのポイント | 具体的な対応 |
|---|---|
| すぐに抱き上げない | 自分で起き上がる機会を与える |
| 様子を見る | 大丈夫か、痛くないか表情や仕草で確認する |
| 大丈夫だよと声かけ | 「転んじゃったね、大丈夫だよ」と安心させる |
| 自分で起き上がれたら褒める | 「すごいね!頑張ったね!」と肯定的に伝える |
| 安全な環境を用意しておく | 転んでも大きな怪我にならないように対策しておく |

転ぶ経験は、赤ちゃんが自分で立ち上がる力や危険回避能力を身につける機会になります
危険でない限りは、赤ちゃんの「自分でやる」気持ちを大切に見守りましょう。
成長を見守るあたたかい気持ち
赤ちゃんの歩き始めの時期やペースには、個人差があります。
他の子と比べるのではなく、目の前にいるお子さんの成長をそのまま受け止めるあたたかい気持ちで見守ることが、保護者の方にとっても、赤ちゃんにとっても大切です。
歩き始めるまでのハイハイやつかまり立ち、伝い歩きといった一つ一つの過程は、赤ちゃんが歩くために必要な力を積み重ねている大切な時間です。
その子ならではのペースを理解し、それぞれの成長段階を応援しましょう。
| 見守る心構え | 大切なこと |
|---|---|
| 個人差を受け入れる | 他の子と比べず、その子のペースを尊重する |
| 焦らない | 成長の過程を楽しむ |
| ポジティブな声かけ | 「頑張ってるね」「すごいね」と肯定的に話しかける |
| 不安な時は相談する | 健診や専門機関に頼ることをためらわない |
| 過程を喜び合う | つかまり立ちや伝い歩きも成長として喜ぶ |

「うちの子のペース」を大切に、成長の道のりをあたたかい気持ちで応援しましょう
一緒に成長を喜び合い、楽しい思い出をたくさん作ってください。
よくある質問(FAQ)
- Q赤ちゃんが歩き始める時期は具体的にいつ頃ですか?
- A
多くの赤ちゃんは生後11ヶ月から1歳3ヶ月頃に初めて一人で数歩歩くようになります。
これはあくまで一般的な平均的な目安の時期です。
早い子では10ヶ月頃から、ゆっくりな子でも1歳半頃までに歩き始めることが多いようです。
- Qなかなか歩き始めない場合、どんな原因が考えられますか?
- A
赤ちゃんがなかなか歩き始めないのは、生まれ持った気質(例えば慎重な性格)や、ハイハイを十分に経験して体の準備に時間をかけていることなどが原因として考えられます。
また、歩行までの発達ペースには大きな個人差があります。
他の発達(首すわり、お座り、ハイハイなど)が順調であれば、多くは心配いりません。
- Qハイハイをあまりしない赤ちゃんは歩き始めるのが遅くなりますか?
- A
ハイハイをたくさんすることは、体のバランス感覚や筋力を養う上でとても大切です。
そのため、ハイハイの期間が短かったり、あまりしない赤ちゃんの中には、歩き始めが少し遅くなるケースもあります。
しかし、これはすべての場合に当てはまるわけではなく、ハイハイ以外の動きで体をしっかり鍛えている赤ちゃんもいます。
- Q赤ちゃんの歩行練習はどのように行えば良いですか?
- A
赤ちゃん自身の「歩きたい」という意欲を育むことが最も大切です。
赤ちゃんの手を持って一緒に数歩歩いてみたり、少し離れた場所におもちゃを置いて誘導したりすることが有効な方法です。
成功体験を褒めることで、赤ちゃんは自信を持って取り組みます。
安全な環境を整え、無理強いせず、遊びを通して体を動かす楽しさを伝えることを意識してください。
- Qファーストシューズはいつ頃から履かせれば良いですか?
- A
ファーストシューズは、赤ちゃんが屋外で歩き始める頃になったら準備を検討しましょう。
まだ室内中心であれば裸足や滑り止め付きの靴下で十分です。
屋外で歩く際には、アスファルトなどの刺激から足を守り、安定した歩行をサポートするために適切なファーストシューズを履かせます。
- Q歩き始めの赤ちゃんがよく転ぶのは心配いりませんか?
- A
歩き始めの赤ちゃんが転ぶのは自然なことであり、心配はいりません。
転ぶことで、赤ちゃんは体の使い方やバランスの取り方を学びます。
これは歩行の発達過程において非常に重要な経験です。
安全な場所であれば、転んでもすぐに駆け寄らず、自分で起き上がろうとする様子を見守ることも大切です。
ただし、頭を強く打つなど、明らかな危険がある場合はすぐに助けてください。
まとめ
この記事では、赤ちゃんが一人で歩き始める一般的な時期や、それに先立つサイン、もし歩き始めが遅くても大丈夫なケース、そして親御さんができるサポート方法についてお伝えしました。
赤ちゃんの成長には大きな個人差があります。
- 赤ちゃんが歩き始める時期の一般的な目安は11ヶ月から1歳3ヶ月頃、しかし個人差が大きい点
- 歩行の準備段階で見られるつかまり立ちや伝い歩きなど具体的なサイン
- 1歳を過ぎても焦る必要はないこと、心配なサインの見極めと専門機関への相談の重要性
- 安全な環境作り、働きかけ、適切な靴選びによる赤ちゃんの歩行サポート方法
今日から、お子さんのペースを大切に見守りながら、安全な環境で歩行の準備をサポートしてあげてください。
必要であれば、専門機関へ相談することも安心につながります。