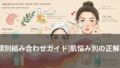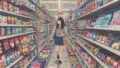「4人も子育てできてすごいですね!」そう言われるたび、心の中で大変だと感じていませんか。
完璧な親になろうと頑張りすぎて、疲れていませんか。
多子育児で日々手探りの私ですが、試行錯誤の中で気づいたのは、子どもが多ければ多いほど「完璧な育児」にこだわる必要はないということです。
この記事では、多子育児で完璧をやめた私のリアルな体験談をお伝えします。
肩の力を抜いて「まぁ、いっか」と思えるようになったら、心がふっと軽くなりました。
それだけでなく、子どもたちが自分で考え、行動するようになり、予想もしなかった素晴らしいギフトを受け取ることができたのです。
完璧を手放すことが、親である私を楽にしてくれ、子どもたちの自立を促すきっかけとなりました。

多子育児は完璧じゃなくても大丈夫だと気づけました。
- 多子育児で完璧を目指すことの大変さの理由
- 筆者が「完璧な親」を手放すために意識的にやった具体的なこと
- 「まぁ、いっか」と思ったら子どもたちが自分で考え行動するようになったリアルな体験談
- 完璧じゃない育児が子どもも親も自分らしく輝かせる理由
- 肩の力を抜いたら見えた多子育児の思わぬギフト
- 多子育児のリアル体験談:なぜ**完璧**を目指すのは大変なのか
- 私が「完璧な親」を手放すために意識的にやったこと
- 「まぁ、いっか」で子どもたちが自分で考え行動するように
- 完璧じゃない育児が子どもも親も輝かせる
肩の力を抜いたら見えた多子育児の思わぬギフト
多子育児の毎日の中で一番重要だと感じていることは、「完璧を目指さない」と決めることです。
この決断によって、親の心は軽くなり、予想もしなかった素晴らしいギフトを子どもたちから受け取ることができました。
この見出しでは、多子育児のリアルな本音として「大変」さを認め、そこから「完璧を手放す」ことで心が軽くなった瞬間、そして「まぁ、いっか」という魔法のような思考が育児の視野を広げてくれること、さらに「子どもからの予想外のギフト」について詳しくお伝えします。
多子育児は確かに忙しい毎日です。
しかし、肩の力を抜いて完璧を手放すことで、子どもたちは自分で考え行動するようになり、その成長が親にとって何よりのギフトとなって返ってくるのです。
多子育児は「すごい」より「大変」が本音
「4人も子育てしていてすごいですね」と言われることがよくあります。
そんな時、心の中では「すごい」というより「大変」が正直な本音なのだと感じます。
毎日、朝から晩まで慌ただしく時間が過ぎ、子どもたちの世話、家事、仕事と、やることは山積みになります。
一人ひとりの子どもとじっくり向き合う時間もなかなか取れず、手が足りないと感じることばかりです。
大変なのが、多子育児の普通の姿なのだと感じています。
子どもが複数いれば、単純に手間や時間は増えるものです。
この大変さを無理に否定せず、まず「大変なのが当たり前だ」と受け入れることが大切だと気づきました。
「完璧」を手放したら心が軽くなった瞬間
子育てにおける「完璧」とは、いつも笑顔で子どもに優しく接し、栄養バランスの取れた食事を毎日作り、家は綺麗に片付いていて、子どもの教育にもしっかり時間をかける、といった理想像のことかもしれません。
私は長い間、この「完璧な母親」を目指して、自分を追い詰めていました。
しかし、多子育児の現実は、その理想とはかけ離れた毎日でした。
ある日、手抜きの夕食でも子どもたちが「美味しいね」と笑顔で食べているのを見た時、「これでいいんだ」と心がふっと軽くなるのを感じたのです。
部屋が少し散らかっていても、子どもたちがリビングで楽しそうに遊んでいるのを見て、「完璧な片付けより、みんなが笑顔でいられる空間の方が大切だ」と思えました。

完璧を目指すのをやめると、心に風が通るように軽くなることがあります。
「〇〇でなければならない」という固定観念を手放すことで、心の余裕が生まれるのを実感しました。
完璧を手放した瞬間から、育児が少しずつ楽になっていったのです。
育児の視野が広がる「まぁ、いっか」の魔法
子育て中の「まぁ、いっか」という言葉は、少しネガティブな響きに聞こえるかもしれません。
しかし、この言葉には、固くなっていた心を解きほぐし、育児の視野を一気に広げてくれる魔法のような力があると感じています。
以前は、少しの汚れや失敗にも目くじらを立てていましたが、「まぁ、いっか」と思えるようになってから、子どもの試行錯誤を見守れるようになりました。
例えば、子どもが自分で卵を割って失敗しても、「まぁ、いっか、次があるさ」と見守ることで、自分でできるようになるプロセスを見届けられるようになりました。
完璧な結果だけを見ていた視野から、子どもが自分で考え、自分でやってみるという成長の過程が見えるようになったのです。

『まぁ、いっか』という思考は、育児の新たな景色を見せてくれます。
「まぁ、いっか」と肩の力を抜くことで、これまで見えなかった子どもの素晴らしい一面や、育児の中の小さな幸せに気づけるようになります。
この心の変化が、毎日の育児をより豊かなものに変えてくれると感じています。
予想外の形で返ってくる子どもからのギフト
子育てで得られる「ギフト」と聞くと、親孝行や感謝の言葉などを想像するかもしれません。
もちろんそれも嬉しいものですが、多子育児で私が受け取ったギフトは、もっと予想外で、日々の生活の中に散りばめられていました。
それは、親が完璧を手放し、少し手や口出しを減らしたことで、子どもたちが自ら考え、行動するようになった姿のことです。
子どもたちが自分で考え行動するようになった具体的な例を以下に示します。
| ギフトの内容 |
|---|
| 残り物で自分でご飯を作る姿 |
| 自分の持ち物を自分で管理する姿勢 |
| きょうだい同士で助け合う場面 |
| 親を気遣う優しい言葉 |
これらの子どもたちの自立や思いやりの行動は、私が「ちゃんとしなきゃ」と必死だった時にはあまり見られなかったものです。
「自分でやりなさい」と口で言うより、親が少し手放すことで、子どもたちは驚くほど成長するのだと気づきました。

子どもたちが成長し、自ら考え行動する姿こそが、最高のギフトです。
子どもたちの「自分でできた」という達成感に満ちた笑顔や、きょうだいがお互いを思いやる姿を見るたびに、私の心は温かい気持ちで満たされます。
完璧ではない育児を通して、私は子どもたちからたくさんの希望と喜びをもらっていると感じています。
多子育児のリアル体験談:なぜ**完璧**を目指すのは大変なのか
子どもが4人いると、「すごいね」「大変でしょう」とよく言われます。
たしかに大変ですし、私はいつも完璧を目指そうとして、その重さに押しつぶされそうになっていました。
多子育児で完璧な親になれないと感じる大きな理由は、毎日が時間との戦いで余裕がなく、きょうだいそれぞれのニーズに応えられない焦りを感じるからです。
さらに、周囲からの期待と自分を追い詰めるプレッシャー、そして理想の子育て像と現実の大きなギャップが、私たちを追い詰めていくのです。
多子育児において完璧を目指すことは、現実的に難しく、自分自身を必要以上に苦しめてしまう原因となります。
毎日が時間との戦いキャパオーバー寸前
多子育児は、文字通り「毎日が時間との戦い」です。
朝起きた瞬間から夜眠りにつくまで、怒涛のように時間が過ぎていきます。
4人の子どもたちの朝の支度、食事、学校や園への送迎、帰宅後の宿題や習い事、夕食、お風呂、寝かしつけと、やることリストは常にいっぱいです。
例えば、朝5時半に起きてお弁当作りから始まり、子どもたちが寝る夜10時頃まで、自分のための時間は数分あるかないかという状態が日常です。
一人にゆっくり絵本を読んであげる時間も、じっくり話を聞いてあげる時間もなかなか確保できません。
この時間的な制約が、常に「キャパオーバー寸前」の精神状態を生み出しています。
| やることリスト | 時間の制約 |
|---|---|
| 朝食・お弁当作り | 複数人の支度と同時に進行 |
| 送迎 | 年齢や場所が異なり移動が多い |
| 宿題・勉強 | 一人一人に違うサポートが必要 |
| 夕食準備・片付け | 量が多く、時間もかかる |
| 入浴・寝かしつけ | 年齢によって手順が異なり手がかかる |

いつも時間に追われて心に余裕がありません
このように、多子育児は時間管理が極めて難しく、時間に追われることで精神的な余裕を失いがちになります。
きょうだいそれぞれのニーズに応えられない焦り
子どもが複数いると、当然ながら「きょうだいそれぞれのニーズ」が異なります。
年齢や個性、その日の体調によって、求めるサポートはさまざまです。
小学生、中学生、そして未就学児と年齢が離れている場合、同時に違うことを求められる場面が多くあります。
例えば、長男から「この問題教えて」、次女から「今日の出来事聞いて」、三男から「一緒に遊んで」、末っ子から「抱っこ」と同時に言われることがあります。
一度に複数の要求に応えるのは難しく、誰かのニーズを後回しにせざるを得ません。
一人一人と深く向き合ってあげる時間が取れないことに対して、親としての焦りや申し訳なさを感じます。
| きょうだいのニーズ例 | 対応の難しさ |
|---|---|
| 勉強のサポート | 内容が異なり、集中して教える時間がない |
| 学校や友達の話を聞く | じっくり聞く時間や気持ちの余裕がない |
| 一緒に遊ぶ・相手をする | 他の子どもの世話や家事に追われる |
| 甘える・抱っこする | 全員に十分に応える物理的な制約 |

一人一人に丁寧に向き合ってあげられないと感じます
このように、きょうだい一人一人の異なるニーズに十分に応えられない現状が、親の心に重くのしかかり、完璧な親像からかけ離れていると感じる原因となります。
周囲からの期待と自分を追い詰めるプレッシャー
多子育児をしていると、周囲から「すごいね」と褒められる機会が多いです。
しかし、その言葉の裏に、「ちゃんとしていて当たり前」「大変なのに完璧にこなしているんだろう」といった「周囲からの期待」を感じることがあります。
善意で言ってくれる言葉でも、「すごい」と言われるたびに、「この期待に応えなければ」「大変な素振りを見せてはいけない」という「自分を追い詰めるプレッシャー」に変わってしまうのです。
例えば、子どもたちの服装や持ち物が少し乱れていたり、テストの成績が悪かったりすると、「多子家庭だから仕方ない」と思われたくないと感じてしまいます。
自分自身の心の中にも、「完璧な親であるべきだ」という強い思い込みがあり、外部からの期待と内なるプレッシャーが相まって、苦しくなります。
| プレッシャーの要因 | 具体的な状況 |
|---|---|
| 周囲からの「すごいね」 | 期待に応えようと必要以上に頑張る |
| 子どもの状態への周囲の視線 | 行き届いていないと思われることへの懸念 |
| 自分の中の「べき思考」 | 理想の親像から外れることへの自己嫌悪 |
| ママ友や親戚からのアドバイス | 自分のやり方を否定されたように感じる |

周囲の言葉や自分の思い込みに縛られて苦しくなります
外部からの期待と、自分自身の内なる「こうあるべき」という思い込みが、多子育児のリアルな大変さに追い打ちをかけ、完璧主義から抜け出せなくさせてしまうのです。
理想の子育て像と現実の大きなギャップ
多くの親は、頭の中に「理想の子育て像」を持っています。
絵本に出てくるような穏やかな家庭、子ども一人一人と丁寧に向き合い、手作りのご飯を囲む食卓、いつも笑顔で時間に追われない自分。
しかし、多子育児の「現実」は、その理想からかけ離れていることがほとんどです。
実際には、毎日時間に追われ、つい子どもに強い口調で言ってしまったり、栄養バランスよりも手軽さを優先して食事を作ったり、家の中が常に片付かない状態だったりします。
例えば、「寝る前に静かに絵本を読んであげる」が理想でも、現実は全員を時間内に寝かせるためにバタバタになり、絵本を省くこともしばしばです。
この「理想と現実の大きなギャップ」に直面するたびに、自分はダメな親だと自己嫌悪に陥り、ますます完璧を目指そうとしてしまい、さらに苦しくなります。
| 理想の子育て像 | 多子育児の厳しい現実 |
|---|---|
| いつも笑顔で穏やかな親 | イライラして感情的になることが多い |
| 手作りのバランス良い食事 | 冷凍食品や総菜、外食に頼る日がある |
| きれいに片付いた家 | 子どもたちの物で常に散らかっている |
| 子どもと丁寧に向き合う時間 | 一人一人とゆっくり話す時間がない |
| ゆとりのある一日のスケジュール | 朝から晩まで時間に追われ、バタバタする |

理想が高すぎるほど、現実とのギャップに打ちのめされます
このように、理想と現実の間に大きな隔たりがあることに気づくとき、完璧な親になれない自分を責めてしまい、多子育児の精神的な負担がさらに増大するのです。
私が「完璧な親」を手放すために意識的にやったこと
「ちゃんとしなきゃ」という気持ちが強いほど、自分を追い詰めてしまいます。
多子育児の毎日は時間との戦いで、すべてのことに完璧を目指すのは不可能でした。
私が自分自身を追い詰める「完璧な親」を手放すために、意識的にやめたことを具体的に紹介します。
私がやめたことは、毎日の献立をきっちり決めること、「毎日の献立決めを諦めた」。
部屋を隅々まで片付けたり掃除したりすること、「部屋の片付けや掃除を最低限にした」。
子どもたちの持ち物を毎回チェックすること、「子どもたちの持ち物チェックをやめた」という、家事や育児の「当たり前」でした。
さらに、「〜しなきゃ」という自分を縛る考え方自体を見直し、「「しなきゃ」思考を手放すマイルール」を決めました。
完璧を手放したら、想像以上に心が軽くなり、子どもたちが自分で考えて行動するようになりました。
私が「やめたこと」は、結果として家族全員にとって良い方向に進むきっかけになったと感じています。
毎日の献立決めを諦めた
「毎日の献立決め」は、多くの親御さんが頭を悩ませることだと思います。
私も以前は「今日の夕食は何にしよう」「栄養バランスは大丈夫かな」と毎日考えていました。
でも、考えている時間も献立を買い物に行く時間も、多子育児にはありませんでした。
子どもたちも好き嫌いがあり、せっかく作ったのに食べてくれないこともあり、どんどん気持ちがすり減っていきました。
そこで、完璧な献立を毎日考えることをやめる決意をしたのです。
具体的なやり方として、
- 1週間分の献立をまとめて決めず、その日あるものや特売品で決める
- 週に数回は、子どもたちが自分で食べられるものを用意して各自で食べる「セルフごはんの日」にする
- 冷蔵庫の残り物や常備菜、冷凍食品などを積極的に活用する
- 完璧な栄養バランスは気にしすぎない
私が献立決めを「諦めた」ことで、買い物や調理の負担が減り、何より「ちゃんと作らなきゃ」というプレッシャーから解放されました。
驚いたことに、子どもたちは文句を言うどころか、「今日は自分で作る!」と言って簡単なものを作るようになったり、冷蔵庫のものを工夫して食べたりするようになりました。

献立は完璧でなくても、家族の負担が減ることが大切です。
毎日の献立に縛られず、柔軟に対応することで、調理時間の短縮にもつながり、子どもたちも自分で食べるものを選ぶ練習になりました。
完璧を目指す必要は全くありません。
部屋の片付けや掃除を最低限にした
多子世帯では、家の中があっという間に散らかります。
「掃除が行き届いた綺麗な家」を保つことは、私にとっては非常に難しく、いつも「片付けなきゃ」「掃除しなきゃ」という焦りを感じていました。
しかし、完璧にしようとするほど疲れてしまい、散らかった家を見るたびにイライラ募りました。
この状況を変えるために、部屋の片付けや掃除の基準を思い切って下げてみることにしました。
具体的に最低限にしたこととして、
- 毎日全ての部屋を掃除機がけせず、気になる場所だけをさっとかける
- 水回りの掃除も毎日せず、汚れが目についた時に行う程度にする
- 完璧な収納を目指さず、ざっくりと片付いていれば良しとする
- 子どもたちにも簡単な片付けは手伝ってもらう
以前は、床に物が落ちているのが許せず、常に何かを拾ったり片付けたりしていました。
でも、最低限にすることにしてからは、多少の散らかりは見ないふりをするようにしました。
物理的な負担が減ったことはもちろん、心の負担が大きく軽減されたのです。
「全部やろう」としないことで、掃除に追われる感覚がなくなり、自分を責めることが減りました。

家が多少散らかっていても、心の平穏の方がずっと大切です。
完璧な家を保つことに時間や労力を費やすのではなく、自分自身がリラックスできる時間を少しでも作ることを優先することで、子育て全体に対しても穏やかな気持ちで向き合えるようになりました。
子どもたちの持ち物チェックをやめた
学校や習い事の持ち物チェックは、以前は私の仕事だと思っていました。
「忘れたら大変」「親として確認しなきゃ」という思いが強く、毎日子どもたちが寝た後にこっそりチェックしていました。
しかし、子どもが4人となると、持ち物の量も種類も膨大です。
毎日全員分を完璧にチェックするのは深夜までかかり、寝不足になることも少なくありませんでした。
ある時、「いつまで私がやるんだろう」と思ったのが、やめるきっかけでした。
具体的にやめたこととして、
- 翌日の準備は子ども自身に完全に任せる
- 「忘れ物ない?大丈夫?」と声かけをするだけにする
- 忘れ物をしても、まずは子ども自身にどうするか考えさせる
- 親が代わりに届けることは極力しない
最初は忘れ物もしました。
体操服を忘れて体育が見学になった、道具を忘れて習い事ができなかった、といったこともありました。
でも、忘れ物をした経験から、子どもたちは自分で「困る」ことを学びました。
すると、次のからは自分で持ち物リストを見たり、前日の夜や朝に自分で確認したりするようになったのです。
きょうだい同士で「〇〇持った?」と声をかけ合っている姿も見られるようになりました。

子どもを信じて任せることで、自分で責任を持つ力が育ちます。
子どもたちの持ち物チェックをやめたことは、彼らが自分で考えて行動する力を大きく伸ばす機会になりました。
私は心配を手放し、子どもたちの「できる」を信じることができるようになりました。
「しなきゃ」思考を手放すマイルール
多子育児の毎日には、「あれもしなきゃ、これもしなきゃ」という考えが次々と浮かんできます。
でも、その「〜しなきゃ」は、本当に必要なことなのか、誰かに強いられているのか、立ち止まって考えることが大切です。
私の場合、「ちゃんとしたお母さんに見られなきゃ」「子どものために全てを犠牲にしなきゃ」といった漠然とした「〜しなきゃ」が自分を苦しめていることに気づきました。
これらの思考を手放すために、自分なりのマイルールを決めました。
具体的に決めたマイルールとして、
- 「〜しなきゃ」と思ったら、「本当に?」と自分に問いかける時間を作る
- 完璧でなくても「まぁ、いっか」と思える基準を自分の中で持つ
- 疲れている時は無理せず、家事や育児の手を抜くことを自分に許可する
- 自分のための時間(休息、好きなこと)を意識的に作る
- 他の多子育児の親御さんの「手抜き体験談」を参考に、自分も試してみる勇気を持つ
このマイルールを持つことで、「ちゃんとしなきゃ」という強迫観念から少しずつ解放されていきました。
できない自分を責めるのではなく、「今日はこれが精一杯」「これでも十分」と思えるようになったのです。
自分に優しくなれたことで、心に余裕が生まれ、子どもたちにも以前より穏やかに接することができるようになりました。

自分を縛る「〜しなきゃ」を手放して、自分に優しいルールを持ちましょう。
「しなきゃ」思考を手放し、自分に合ったマイルールを持つことで、育児のプレッシャーから解放され、もっと前向きな気持ちで毎日を送れるようになります。
「まぁ、いっか」で子どもたちが自分で考え行動するように
多子育児で完璧な親を手放したことで、親が楽になっただけでなく、子どもたちに素晴らしい変化が見られました。
最も重要な変化は、子どもたちが親に言われなくても自分で考え、行動するようになったことです。
それは、食事の支度や身の回りのこと、きょうだい間の関わりまで、日々の生活のさまざまな場面で実感できます。
親が手放したことで具体的に何が起きたのか、次の見出しで詳しくお話ししますね。
残り物で自分でごはんを作るきょうだいの姿や、自然に自分のことは自分でやる習慣が自然に生まれたこと、そしてきょうだい同士で教え合い助け合う姿から、親が手を出さないことで子どもたちの問題解決力がどのように育つのかをお伝えします。
完璧を手放し「まぁ、いっか」と思えるようになったことは、子どもたちの主体性と問題解決能力を引き出すきっかけとなり、彼らの成長を力強く後押ししてくれたのです。
残り物で自分でごはんを作るきょうだい
料理が苦手なわけではありませんが、毎日全員が納得する凝ったメニューを用意するのは難しいことでした。
毎日「これ美味しい!」「これ食べたくない!」の応酬で、食事の時間がストレスに感じることもありました。
そこで「まぁ、いっか。
あるもので何とかしてもらおう」と、献立をきっちり決めたり、すべて親が用意したりすることをやめてみました。
すると、ある休日のお昼、子どもたちだけで冷蔵庫を開けて、残っていたご飯と野菜、卵などを使ってチャーハンを作り始めたのです。
冷蔵庫にあるもので何が作れるかを話し合い、協力しながらキッチンに立つ姿を見て、驚きとともに嬉しさを感じました。
彼らは親に頼ることなく、自分たちの空腹を満たすために工夫し、行動しました。

自分たちの食事を自分たちで何とかする力が育ったのだと感じました
親が「ちゃんと作らなきゃ」を手放したことで、子どもたちは自分たちで食を賄う工夫を身につけたのです。
自分のことは自分でやる習慣が自然に生まれた
以前は、子どもたちの部屋の片付けや学校の準備も、つい手を出してしまうことがありました。
部屋が散らかっていると気になって指示を出したり、忘れ物がないか親がチェックしたり。
ですが、私の体力には限界があります。
すべてに目を行き届かせるのは無理だと気づき、「まぁ、いっか。
自分で管理できるようになってほしい」と、お世話を焼きすぎるのをやめました。
最初は少し不安もありましたが、驚いたことに、子どもたちは自分で考えて動き始めました。
翌日使う教科書や宿題を自分で揃え、部屋も遊びやすい程度には片付けるようになりました。
たまに探し物をしたり、「あれどこ?」と聞かれたりすることもありますが、自分で探すか、きょうだいに聞くように促しています。

親が手出し口出しをやめたことで、子どもたちは自分の管理は自分でやるものだと理解しました
親が完璧な管理をやめたことで、子どもたちは自身の持ち物や空間に責任を持つようになったのです。
きょうだい同士で教え合い助け合う姿
子どもが4人いると、それぞれ得意なことと苦手なことがあります。
勉強も、遊びも、お手伝いも、レベル感はバラバラです。
以前は、私が一人ひとりに合わせて教えたり、手伝ったりしようとしていましたが、時間も体力も足りません。
そこで「まぁ、いっか。
きょうだいで何とかするだろう」と、全てに私が介入するのをやめました。
宿題でわからないところがあると、自分より得意なきょうだいに聞きに行ったり、難しい組み立てのおもちゃを皆で協力して完成させたりする姿が見られるようになりました。
誰かが困っていると、自然ともう一人が手を差し伸べることもあります。
もちろん、時にはケンカもしますが、自分たちで解決策を見つけるための重要なプロセスだと捉えています。

親が出しゃばらないことで、子どもたちはきょうだい間で学び合い支え合う関係を築きました
きょうだいが多い環境で親が全てを管理しないことで、子どもたちは自然な助け合いと協力の精神を育んだのです。
親が手を出さないことで育つ問題解決力
これまでお話ししたような、残り物でご飯を作ること、自分の身の回りのことを自分で管理すること、そしてきょうだいと協力すること。
これらはすべて、子どもたちが日常生活の中で直面する小さな「問題」です。
親が先回りして解決するのではなく、「まぁ、いっか。
自分でやってみよう」と見守ることで、子どもたちはどうすれば良いかを自分で考え、試行錯誤し、行動する経験を積み重ねます。
失敗することもありますが、そこから学び、「次はこうしてみよう」と改善していく力を身につけていきます。
例えば、チャーハンが上手くできなかったら「次はもう少し油を多めにしてみよう」と考えたり、忘れ物をして困ったら「明日は前日の夜に準備しよう」と工夫したりするようになります。
これらの経験は、学校での勉強や将来社会に出た時にも必要とされる、生きるための問題解決能力の基盤となります。

親が子どもたちの問題にすぐ手を出さないことが、彼らの考える力と行動力を育む最も効果的な方法の一つだと学びました
親が「まぁ、いっか」と手放すゆとりが、子どもたちの自立心と、困難に立ち向かう力を育む大切な栄養となったのです。
完璧じゃない育児が子どもも親も輝かせる
多子育児で「完璧な親」を目指す必要はありません。
「ちゃんとしなきゃ」を手放し、少し肩の力を抜くことこそ、子どもと親の双方が自分らしく輝くための鍵となります。
あなたが笑顔でいること、そして親が完璧を手放すことで見えてくる子どもの意外な一面や成長、不完全さから生まれる家族の絆。
「大変さ」の中に「楽しさ」を見つけるためのヒントを順に記述します。
肩の力を抜いた育児は、決して「手抜き」ではありません。
あなた自身が心穏やかでいられることで、子どもたちも安心し、家族全体が温かい空気に包まれます。
完璧じゃない育児だからこそ得られる豊かさがあるのです。
親が笑顔でいることの重要性
親の笑顔は、子どもにとって何よりの安心材料となります。
いつも追われるように忙しく、焦りやイライラが見える親の顔を見ていると、子どもは「自分が何か悪いことをしたのではないか」「甘えてはいけない」と感じてしまうことがあります。
心に余裕がなく、つい強い口調になってしまう。
そんな時、子どもは委縮したり反発したりすることが多いです。
逆に、親がゆったりと構え、笑顔で接する時間が増えると、子どもは安心して自分の気持ちを表現できるようになり、親子関係も良好になります。
ある調査では、親が笑顔でいる時間の多い家庭の子どもは、情緒が安定しているという結果が出ています。

親の笑顔は子どもの心の栄養になります
あなたが完璧を手放し、自分の心にゆとりを持つことが、結果として子どもたちに安心感を与え、健やかな成長を促す最高のプレゼントになります。
子どもの意外な一面や成長を発見する喜び
完璧を目指して先回りし、全てを管理しようとすると、子どもたちの隠れた力や可能性に気づきにくくなります。
親が少し手綱を緩めた時にこそ、子どもたちは自ら考え、驚くような行動を示すことがあります。
例えば、食事の準備が間に合わない時、小学生の子どもが冷蔵庫の残り物で簡単なものを作ってくれたり、きょうだい同士で協力して準備を進めたりすることがあります。
学校の持ち物チェックをやめたら、最初は忘れ物が増えても、きょうだいに教えてもらったり自分で確認したりするようになり、次第に自分で管理する力が身につきます。
これは、親が「あれは?」「これは?」と全て指示していたら決して見られなかった姿です。
多子育児では、上の子が下の子の面倒を見たり、困っているきょうだいを助けたりする姿も自然と生まれます。

完璧を手放すと子どもの成長と自立が見えてきます
親が完璧に世話を焼くことをやめた時、子どもたちは環境に適応し、自分で考えて行動する力を驚くほど発揮します。
その成長過程を間近で見守ることは、親にとって大きな喜びとなります。
完璧じゃないからこそ生まれる家族の絆
家族は「完璧であること」を求められる場所ではありません。
お互いの不完全さを受け入れ、助け合いながら生きていく場所にこそ、強い絆が生まれます。
親が疲れている時、子どもたちが自然と家事を手伝ってくれたり、小さな子に優しく接してくれたりします。
失敗や困ったことがあっても、「まぁ、いっか」「次頑張れば大丈夫」と家族みんなで笑い飛ばす。
そのような経験を通して、子どもたちは困っている人に寄り添う心や、困難を乗り越える力を育んでいきます。
お互いの弱さを知っているからこそ、「この家族で良かった」と思える瞬間が増えていきます。
多子家庭では、子ども同士が遊び相手になり、学び合い、喧嘩しながらも絆を深めていきます。

不完全さを受け入れることが家族を強くします
完璧ではない日常の中で、お互いを思いやり、支え合う経験こそが、家族の間にかけがえのない温かい絆を育んでいきます。
「大変だけど楽しい」多子育児を生きるヒント
多子育児は、確かに大変なことがたくさんあります。
時間も体力も消耗し、「もう無理」と感じる日もあるかもしれません。
しかし、視点を変え、「完璧」を手放すことで、大変さの中に楽しさを見出すヒントが見えてきます。
例えば、「食事は毎日手作りでバランス良く」といった理想を手放し、たまにはお惣菜や冷凍食品に頼る。
部屋の片付けも「人が来ても恥ずかしくない程度」で良しとする。
「~しなきゃ」という義務感を手放し、「まぁ、いっか」という魔法の言葉を口にする回数を増やします。
これらの小さな手抜きは、あなたの心と体に休息を与えます。
| ヒント | 具体的な行動例 |
|---|---|
| 「完璧」を手放す | 料理や掃除のハードルを下げる |
| 自分に「まぁ、いっか」 | できなかったことを責めない |
| 子どもを信じる | 手を出しすぎず見守る時間を増やす |
| 小さな「楽しい」を見つける | 子どもの面白い言動に注目する時間を取る |

完璧を手放して少しだけ肩の力を抜きましょう
大変さの中から「楽しい」を見つけるためには、まずあなた自身が心にゆとりを持つことが大切です。
「完璧」という重荷を下ろし、子どもたちの成長や家族の日常に隠された小さな喜びを見つけることで、多子育児はもっと楽に、そしてもっと楽しくなります。
よくある質問(FAQ)
- Q完璧主義をやめた育児で、子どもに悪い影響は出ませんか?
- A
親が完璧を目指すのをやめ、肩の力を抜くことは、子どもにとって良い影響を与えることが多くあります。
例えば、親が手出し口出しを減らすと、子どもは自分で考えて行動する機会が増え、自立心や問題解決能力が自然と育まれます。
多少の失敗は経験として、次にどうすれば良いかを学ぶ貴重な機会となります。
完璧ではない親の姿を見せることは、子どもがお互いの不完全さを受け入れ、助け合う姿勢を学ぶきっかけにもなります。
親が心穏やかで笑顔でいる時間が増えることこそ、子どもにとって最も安心できる環境となります。
- Q「まぁ、いっか」と本当に思えるようになるにはどうすればいいですか?
- A
「まぁ、いっか」と思えるようになるには、まず完璧に「しなければならない」という考え方を手放すことが大切です。
「〜しなきゃ」と思った時に、「本当にそれが必要か」「できなくても大丈夫か」と自分自身に問いかけてみてください。
掃除や料理など、全ての家事や育児を完璧にこなすのは多子育児では難しいと認めましょう。
最初は抵抗があるかもしれませんが、小さなことから手抜きや省略を試してみてください。
例えば、献立は凝らず簡単なものにする、部屋の片付けは最低限にするなどです。
完璧ではない自分を許し、「これでも大丈夫」と受け入れる練習を重ねることで、次第に「まぁ、いっか」と心の底から思えるようになります。
- Q多子育児の「隠れた特典」とは具体的に何ですか?
- A
多子育児には、大変さの裏側に隠された特典があります。
それは、子どもたちが互いに学び合い、助け合いながら成長する姿を間近で見られることです。
上の子が下の子の面倒を見たり、きょうだい同士で協力して課題を解決したりする場面は、親が教える以上に彼らの社会性や思いやりを育みます。
また、親が完璧を手放し、全てを管理しないことで、子どもたちは自分で考え、工夫し、行動する力を身につけていきます。
これらの子どもたちの自立的な成長は、親にとって何よりの喜びとなり、多子育児ならではの大きなギフトとなります。
- Q完璧を目指さない育児は「手抜き」とは違いますか?
- A
完璧を目指さない育児は、決してネガティブな意味での「手抜き」ではありません。
それは、限られた時間やエネルギーの中で、本当に大切なこと、つまり子どもたちの心や安全、そして親自身の心身の健康を優先するための「戦略的な育児」と言えます。
掃除や料理、教育に完璧を求めず、最低限で良しとすることで、親自身の心に余裕が生まれます。
その余裕が、子どもたちの話を聞いたり、一緒に笑い合ったりする時間を作るのです。
完璧を目指さないことは、無理なく育児を継続し、家族全員が笑顔で過ごすための前向きな選択となります。
- Qきょうだい一人一人に十分に向き合えないことに罪悪感を感じます。
- A
多子育児において、きょうだい一人一人にたっぷり時間をかけて丁寧に向き合うのが難しいのは、多くの親が感じる現実です。
しかし、大切なのは時間の長さだけではありません。
たとえ短時間でも、子どもが話しかけてきた時に顔を見てしっかりと頷く、宿題を隣で見守る、寝る前に一言だけ「大好きだよ」と伝えるなど、質の高い関わりを意識することが重要です。
また、きょうだい同士の関係性を尊重し、子どもたちが互いに支え合い、学び合う時間を見守ることも大切な「向き合い方」の一つです。
自分自身を責めすぎず、今できる最善を尽くしていると認めましょう。
- Q多子育児の大変さの中で、親が笑顔でいるためには?
- A
多子育児の大変な毎日の中で笑顔を保つためには、まず親自身が無理をしないことが大切です。
完璧を目指すことをやめ、家事や育児に「まぁ、いっか」を取り入れることで、心と体に休息の時間を作り出せます。
また、自分一人で抱え込まず、パートナーや周囲に頼ることも重要です。
短時間でも自分の好きなことやリラックスできる時間を持つことは、心をリフレッシュさせます。
大変さの中に隠されている子どもたちの面白い言動や成長、家族の小さな温かいやり取りなど、日常の小さな「楽しい」に意識的に目を向けることも、笑顔を増やすヒントとなります。
まとめ
多子育児で「完璧な親」を目指して頑張りすぎると、心も体も疲弊します。
この記事では、多子育児のリアルな大変さと、完璧をやめたことで親の心が軽くなり、さらに子どもたちが自分で考え行動するようになった素晴らしい変化をお伝えしました。
- 多子育児における時間や精神的な限界と「完璧な親」を目指すプレッシャー
- 献立決め、掃除、持ち物チェックなど筆者が意識的に手放したこと
- 親が完璧をやめたことで生まれた子どもたちの自立的な行動や工夫
- 完璧ではないからこそ育まれる家族の温かい絆と親子の成長
多子育児は大変さの連続ですが、完璧を手放し「まぁ、いっか」と肩の力を抜くことで、これまで見えなかった子どもたちの力や家族の温かさに気づくことができます。
どうぞ、自分自身にも優しく、目の前の小さな幸せを大切にしながら、あなたらしい子育てを楽しんでください。